
今回お話を伺ったあの人
独立行政法人国際協力機構(JICA)/パレスチナ事務所
京都大学法学部卒。2016年に新卒で独立行政法人国際協力機構(JICA)へ入構。入構3年目でJICA内の新規事業コンテストに応募・採択され、事業の立ち上げを行う。本部での南米地域担当、広島の中国センター勤務を経て、現在はパレスチナに駐在。民間企業と連携しながら、難民支援を行う。
- “貧困から抜け出す手段”としてサッカーをする他国の選手に、大きな衝撃を受けた
- 「君は世界に出て、おもしろいことをやる人間だ」という言葉を真に受けた
- “意識高い系”の中でもがいていた自分を、“デカダンス系”の先輩が救ってくれた
- 「難民支援をしたい」という想いからJICAへ
- 同期とともに新規事業コンペに応募、事業化までこぎつける
- 難民支援のアプローチはひとつじゃない。新しいことをできるポテンシャルがJICAにはある
- まずは自分がハッピーであること。その結果として、誰かの役に立てればそれでいい
TOPICS
“貧困から抜け出す手段”としてサッカーをする他国の選手に、大きな衝撃を受けた
―現在の八里さんのご活躍を紐解くために、まずはルーツについて教えてください。
幼少期から目立ちたがり屋で、人に認められたいという気持ちが人一倍強い子どもでした。そのため、周りからいじめられたり、衝突したりすることも少なくありませんでした。
特にサッカーと勉強では誰にも負けたくないという気持ちが強く、自分はこの両輪で頑張っていこうと思っていました。
小・中学時代はサッカーで県の選抜選手に選ばれ、学校の成績もつねに上位に位置していたので、そこに自分の存在意義があると信じていました。だからこそ、その2つは誰にも負けたくなかったんでしょうね。

しかし、中学2年生のときにサッカーの海外遠征で訪れたブラジルで、自分の存在意義を大きく揺るがす出来事が起こりました。
ある試合で、ブラジルチームと自分たちのチームの試合が引き分けに終わったことがありました。すると相手チームの選手の一人が、その場で泣き崩れたんです。
何故彼はあんなに泣いているのだろうと不思議に思い、通訳の人にその理由を聞いてみると、「試合で結果を残せなかったからクビになったんだ。彼はスラムに逆戻りだね」と言われました。その瞬間、ガツンと頭を殴られたぐらいの衝撃を受けました。
自分にとってサッカーは自己実現・表現の一つでしたが、彼らにとってサッカーは、自分だけでなく、家族も貧困から救える唯一の手段だったんですね。同い年であるにも関わらず、こんな世界で生きている人がいるのか、と衝撃を受けると同時に、自分はプロにはなれないなぁと思いました。
彼らのように、人生のすべてをサッカーには注げないと。
「君は世界に出て、おもしろいことをやる人間だ」という言葉を真に受けた
―その出来事をきっかけに、どのような変化がありましたか。
サッカーでプロにはなれなくても、もう一つの勉強であればなんとかなるかもしれないと思い、進学校に進みました。
サッカーの強豪校に行くという選択肢もあったのですが、結果的には進学校でサッカーを続けるという道を選びました。
小、中学校は地元の公立校に通っていたため、周りに勉強のできる人ばかりがいるというのは初めての経験でした。
しかも、入学して最初のテストの成績は真ん中程度…。今までずっと“天狗”だった自分のメッキがはがれ始めた瞬間でした。
そして相変わらず、サッカー、勉強、そして女の子にモテたいという欲求がとても強かったので、周りとはひんぱんに衝突していました。
今思えば自意識過剰で、変な方向にとがっていましたね(苦笑)。
その後、努力して成績は上位に入ることができたものの、将来やりたいことは決まっていませんでした。
ある日、学校の先生に進路面談で「僕は将来何をやってそうですかね?」と聞いてみたところ、「君はたぶん広い世界に出て、なんかおもろいことをやる人間やと思うで。」と言われ、それを真に受けてしまいました(笑)。
また、母親からは「あんたは理屈っぽいし、つぶしもききそうやから法学部にでも入ってみたら」と言われたこともあり、京都大学の法学部に進学しました。
“意識高い系”の中でもがいていた自分を、“デカダンス系”の先輩が救ってくれた
―大学ではどのように過ごされていましたか。
もともとは、高校時代のチームメイトと大学でも体育会でサッカーをやるつもりでした。しかしそのチームメイトが浪人してしまったため、急にやりたいことがなくなってしまったんですね。
そのときに、「自分がやりたいことはなんやろう」と人生ではじめて真剣に考えました。
幼少期から現在に至るまで、人に認められたいという気持ちが強いことは自覚していたので、それを満たせて自分を納得させられる仕事がいいなと思いました。そのときにふと、“国連職員”というワードが浮かびました。
中学校から大学まで同じところに通い、ある種自分のロールモデルのような存在だった年上のいとこが国連職員を目指していたことも、もしかすると影響していたのかもしれません。
世界で活躍でき、人のために働くことができる国連職員になれば、自分を認めてあげることができるのではないかと思いました。
そして国連職員になるためには、海外の大学院で修士号を取ることと、英語を習得することが有利になると考え、その二つを目標に大学生活をスタートさせました。
まず英語を習得するために京都を英語でガイドするサークルに入ったのですが、いざ外国人と話してみると、英語を聞き取ることもできませんでした。しかも周りのメンバーは英語がペラペラの帰国子女ばかりで、挫折感を味わう日々が続きました。
また、サークル活動のかたわら、高いGPAを取得するために大学の専門分野の勉強にも力を注いでいました。周りにはいわゆる「意識高い系」の人たちが多かったので、自分も頑張らないといけない!と朝から晩まで予定を詰め込んで活動していたのですが、ある日過労で倒れてしまいました。

そのとき自分を救ってくれたのが、「デカダンス系(※)」の先輩でした。サークル活動にはあまり来ないけれど、飲み会と合宿には必ず来る先輩っていますよね(笑)。
ある日、一人の先輩に、「やったほうがいいことはたくさんあるかもしれんけど、その全部を自分がやる必要はないんちゃう?」と言われたときに、気持ちがすごく楽になったことを覚えています。
それ以来、すべてトライして体を壊して周りに迷惑をかけるぐらいなら、自分ができることに集中しようと思えるようになりました。
身体を壊すほど頑張らないといけないと思っていた自分に、「頑張らなくてもいいんちゃうか」と教えてくれた先輩には今でも感謝しています。
(※)…デカダンスは退廃的、虚無的な風潮や生活習慣のこと。
「難民支援をしたい」という想いからJICAへ
―その後、JICAに入構されたきっかけについて教えてください。
イギリスの大学に留学中、セルビア・コソボで国内避難民の物資支援を行ったことがきっかけでした。
国内避難民は難民条約の庇護下に入っていないので、国際社会からも政府からも守られず、厳しい生活を強いられていました。
自分と同じぐらいの年齢の人が、「仕事もないし、お金もないし、希望もない」と言っていた言葉が強く印象に残りました。大学では政治学や国際法を学んでいたので、それらの知識を活かして平和構築を行いたいと思うようになりました。
JICAにはもともと興味を持っており、日本に帰国したタイミングで選考を受け、内定をいただくことができました。
海外での大学院進学と悩みましたが、学費の問題もありましたし、せっかくいただいた機会なので、思い切って入構することに決めました。
―JICA入構後はどのような仕事に携われたのですか。
最初の2年間は本部の中南米部南米課に配属され、南米地域の開発戦略や、政府にお金を貸し付けてインフラを建てるプロジェクトを担当していました。
ブラジルでの経験もあり、もともと南米に興味を持っていたので、南米地域を担当できたことは嬉しかったのですが、予想よりも南米地域は平和でした。
そのため、自分がもともとやりたかった平和構築という観点ではあまり力を発揮できる部分がなく、もやもやした気持ちを抱えたまま過ごすことになりました。
JICAはだいたい2年ごとに異動があるのですが、このまま2年間が終わってしまうのは嫌だと思い、2年目に紛争地域のコロンビアの業務を担当させてくださいと希望を出しました。
希望が通り、自ら新規案件形成のための調査を企画し、現地に行ったりもしたのですが、結局情報収集のフェーズで終わってしまいました。
新しいことにチャレンジできたのはいい経験でしたが、最後までやりきれなかったので心残りはありました。
同期とともに新規事業コンペに応募、事業化までこぎつける
次の2年間は、広島にある中国センターというところに配属されました。
まさか広島に行くことになるとは思ってもいなかったので、配属を聞いたときには正直驚きました。でも、この広島での2年間は自分にとってとてもいい経験だったと思います。
国のインフラ整備に携わっていた南米地域での仕事から一転、広島ではJICA海外協力隊を募集したり、広島の復興経験を紛争影響国の人へどのように伝えていくのかを考えたりするなど、“人くさい”仕事が大半でした。
本部とは違い、のんびりとした雰囲気に最初はカルチャーショックを受けましたが、昼休みにソフトボールをしたりするようなゆるい環境がだんだん好きになっていきました。
―同時期にJICA内での新規事業コンペに応募し、それが採用されたと伺いました。
3年目の頃に、「今のJICAに足りていないことは何か考える」という人事研修があり、同期と何か新しいことをやりたいなと話していました。
ちょうどその頃にJICA内で新規事業コンペがあることを知り、同期たちとアイデアを練って応募しました。
僕たちが提案したのは「JICA Innovation Quest(ジャイクエ)」というオープンイノベーションプラットフォームです。
これまで国際協力に関わりを持っていなかった人々を含め、多様な人々が出会い、共に考える場を創り、新しい国際協力・途上国課題解決のためのアイデアを創りたいという想いから生まれたものです。
ありがたいことにこの案が採用され、2019年度にジャイクエを立ち上げ、現在も同期や後輩によって引き継がれています。若手のみのチームのアイデアが採用されたというのは、後に続く人たちにとっていい実績を残せたのかなと思います。

難民支援のアプローチはひとつじゃない。新しいことをできるポテンシャルがJICAにはある
―現在はどのようなお仕事に携わられていますか。
現在はパレスチナで農業、観光、保健、民間連携といった分野で支援を行っています。
民間連携とは、日本企業と連携をしてパレスチナの社会経済開発を行っていくというものです。最近では、株式会社モンスター・ラボが行っているガザ地区における難民雇用創出のプロジェクトなども担当しています。
自分のキャリアの軸は難民支援でしたが、モンスター・ラボのプロジェクトのように、さまざまなアプローチでの支援がありますし、JICAにはそれができるポテンシャルがあると感じます。
新しいことにチャレンジする中で面食らうこともありますが(苦笑)、いろんな人の価値観を浴びることで頭の天窓が開くことがあり、自分自身それは非常に大切だと思っているので、これからも積極的にチャレンジしていきたいと思います。
まずは自分がハッピーであること。その結果として、誰かの役に立てればそれでいい
―最後に、これからのキャリアを考える人に向けたメッセージをお願いします。 「社会の役に立ちたい」という気持ちも大事ですが、まずは自分がハッピーになれることはなんだろう、と考えてみてほしいかなと。
僕は自分の生活を犠牲にしてまで仕事をしたいとは思っていなくて、まずは自分自身が満足できる人生を送りたいと思っています。その結果として誰かのためになるのであれば嬉しい、というスタンスです。

キラキラ働いている人を見ると焦ることもあるかもしれませんが、まずは自分がハッピーであること。その結果として、誰かの役に立つことができれば十分かなと思っています。必ずしも主人公の立場で活躍する必要はないんじゃないかと。
キャリアについて深く悩んでいる人がいるならば、僕が大学時代の先輩に救われたように、「まぁ、頑張らなくてもいいんちゃう。」という言葉を贈りたいです。
インタビュアー:アイルーツ+(プラス)編集部 小笠原寛
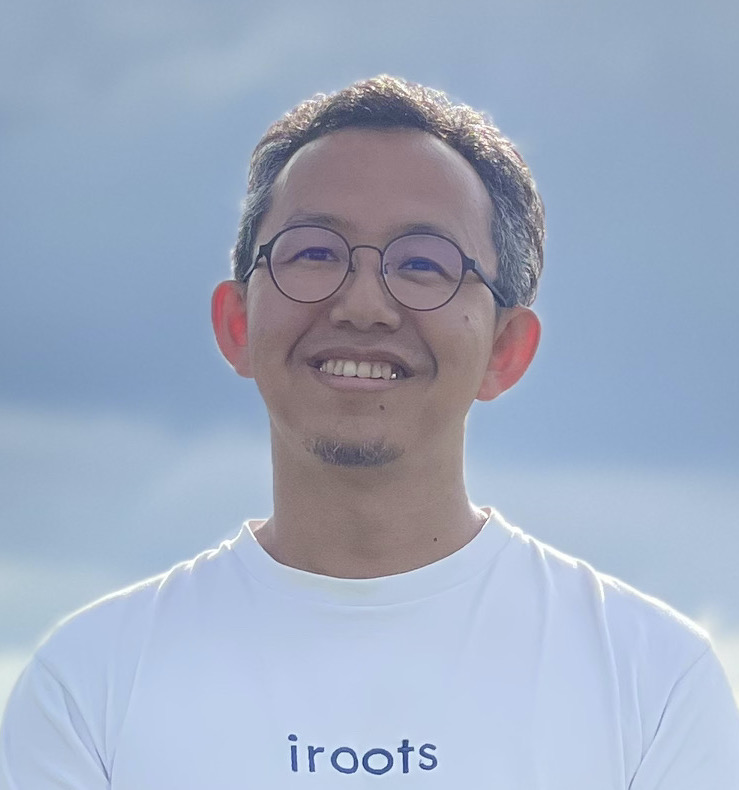
新卒採用責任者他、様々なHR事業経験を積む中で、本音の大切さを実感。
2012年にirootsに参画し、「学生と企業の本音フィッティング」に従事する。
横浜市生まれ、現在は岐阜県関市に在住し、自然と人との対話に耳を傾ける日々。
文・編集:アイルーツ+(プラス)編集部 西村恵

2018年にエン・ジャパンに転籍後、新卒スカウトサービス「iroots」の企画として、
ミートアップやメディアの運営、記事のライティング・編集に携わる。
趣味は映画鑑賞・美術館めぐり。

