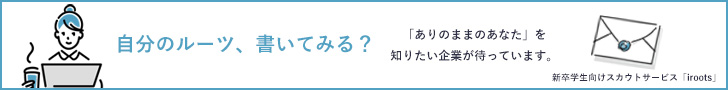新卒スカウトサービス「iroots」を通じて入社した学生は、その後どのように活躍しているのか。企業と学生の「出会い」だけでなく「入社後活躍」の実現を目指すirootsでは、irootsを通じて入社した方々にインタビューをおこない、“その後”の姿に迫ります。
今回は、幅広く社会貢献活動を行っている公益財団法人 日本財団で、公益事業部 国内事業審査チームのメンバーとして活躍する内島さんにお話を伺いました。
Interviewee’s Profile
業界:官公庁・公社・団体、正職員:157名(2025年4月1日現在)
日本財団は、社会課題解決のプロデューサー集団。地方自治体が主催するボートレースの収益金の一部を交付金として受け入れ、国内外の社会課題解決に取り組むNPO団体への資金助成をする民間の団体です。活動資金の助成をするだけでなく、新たな社会課題を見つけ、解決のためのモデルをつくる調査と実践の機能を持つ世界でもユニークな財団。海洋・船舶に関する問題の解決、福祉や教育の向上、災害救援、人道支援や人材育成を通じた国際貢献など、多岐にわたる分野で活動をしている。
内島 駿介(うちじま しゅんすけ)公益事業部 国内事業審査チーム
大学は法学部で法哲学を専攻。学業と並行し、起業・事業売却を経験するほか、ユースセンター運営を通じて若者支援にも携わるなど、旺盛な好奇心を原動力に多様なチャレンジを重ねてきた。就職活動ではM&A業界の企業の内定を得ていたが、irootsのスカウトをきっかけに日本財団の選考を受けることになり、2024年4月に新卒入社。入社後は公益事業部にて助成事業の担当をしながら、新規事業立案にも積極的に取り組んでいる。
- まだ顕在化していない課題に対しても、国や行政、NPO、有識者と解決策を検討し、実践していく
- さまざまな領域の社会課題に関わることができ、オーナーシップを持って取り組めることに魅力を感じた
- さまざまな社会課題の解決に対して興味を持てるような、好奇心旺盛なタイプの方に日本財団は向いている
TOPICS
まだ顕在化していない課題に対しても、国や行政、NPO、有識者と解決策を検討し、実践していく
―最初に、現在のお仕事内容について教えてください。
2024年の入社以来、公益事業部 国内事業審査チームで勤務しています。公益事業部が取り組んでいるのは、国内における公益的な社会課題の解決。例えば、障害者の就労支援や医療的ケア児とその家族を支える仕組みづくり、ヤングケアラー対策、さまざまな困難を抱える子どもたちの支援など、まだ顕在化していない社会課題に対しても、国や行政、NPO、有識者とともに解決策を検討し、実践しています。
このチームで私が担っている役割は大きく二つあります。一つは、日本財団がすでに関わっている活動について、活動の伴走支援や各種事務手続などを行うもの。もう一つが、さまざまな社会課題を調査したうえで、日本財団として新たに取り組む事業を開発するという役割です。私の場合、1年目は日本財団の事業の構造やルール、支援の在り方を掴む必要があるため前者の割合が高かったのですが、2年目に入り事業開発の割合が高くなってきています。
事業開発は、世の中のさまざまな社会課題をリサーチし、日本財団として実施できそうな事業アイデアを考えるところからスタート。その際に重要なのが、日本財団だからこそできることは何かを考えることです。例えば国がすでに取り組んでいること、取り組もうとしていること、民間事業者が取り組むことが望ましいものに私たちが着手することは基本的にありません。行政でも民間でも解決が難しかったり、なかなかアプローチできなかったりする領域こそ、私たちが取り組むべき課題があると考えています。
そういった課題を見つけたら、社内でプレゼンし、フィードバックをもらいながら事業アイデアをブラッシュアップしていきます。最終的にゴーサインが出たら、さまざまな活動を実践していきます。例えば、多くのNPOへの助成を通じて集まる現場の声をもとに共通する新たな社会課題を見出し、その解決策を検討するために有識者を交えた研究会を組成。その成果を政策提言へとつなげたり、実際にモデルとなる事業を自ら実施したりする。そうした形で具体的なアクションを展開していきます。
大きな特徴としては、事業開発をしたからといってずっとやり続けるわけではないということです。国として取り組んでいく事業へと昇華させたり、全国の自治体に仕組みとして取り入れられたり、スタートアップやベンチャーの事業となったりと、どうつなげていくのかも意識しながら取り組んでいます。私はさまざまなことに興味関心があるため、このように幅広く取り組める環境はありがたいですね。
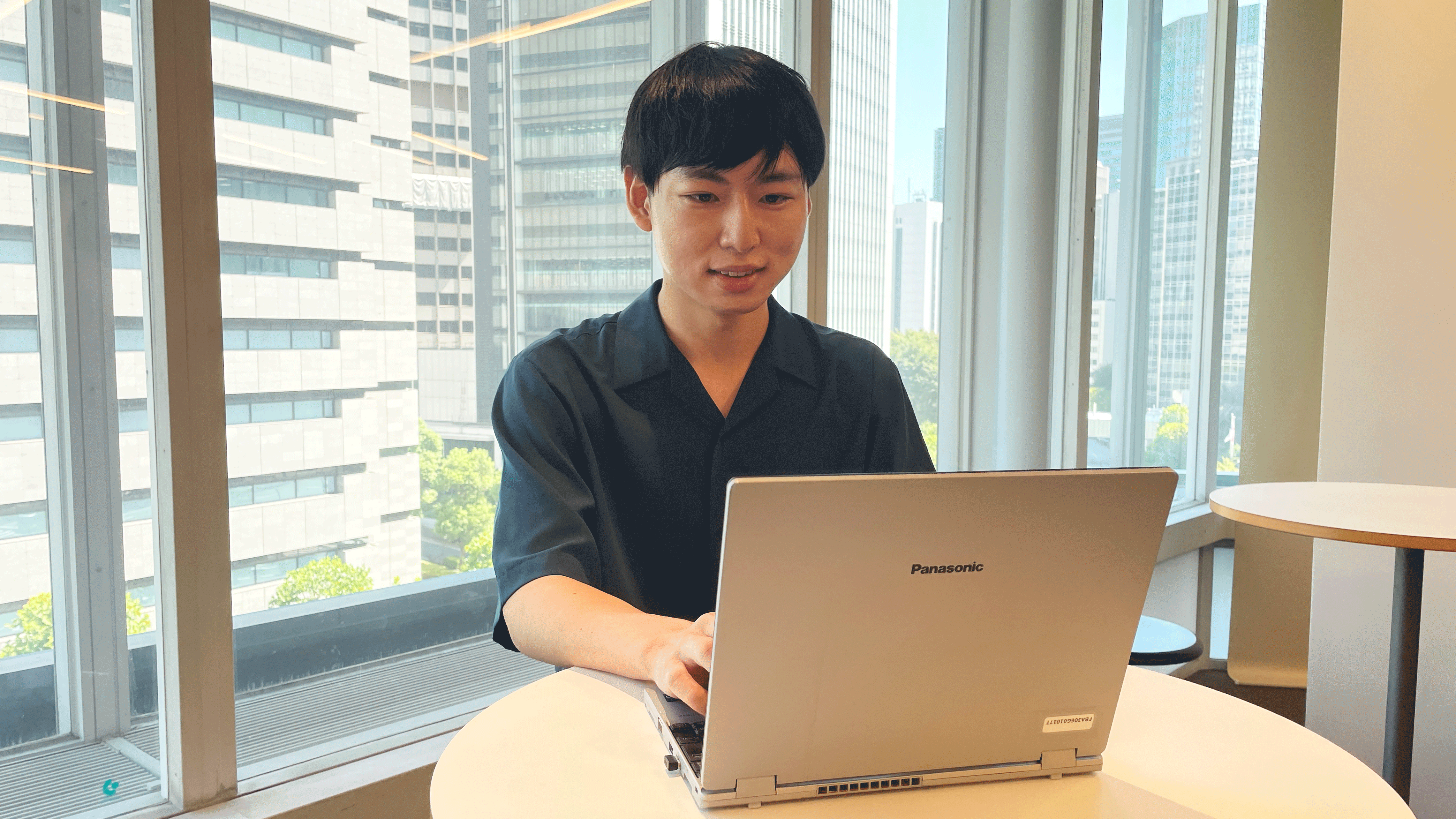
―就活生時代にirootsを使いはじめたきっかけについて教えてください。
学生時代に起業をしていて、三つほど事業を立ち上げました。三つ目の事業がうまくいっていたこともあり、そもそも就活をするかどうか迷っていました。ですので、当初は就活に対するモチベーションが高くなくて、一般的な就活でイメージするような、エントリーシートを提出したり、SPI試験の対策をしたりはしていなかったんです。しかし、周りに合わせて自分も就活やってみようかとスカウト系のサービスにいくつか登録をしました。
そうやっていくつか登録したサービスの一つが『iroots』ですが、使い始めて感じたのがたくさんの情報を記載できるということ。登録したスカウトサービスの中でも一番の情報量だったと思います。自分自身の考えや経験してきたことをしっかり伝えられるという点で、とても魅力的でしたね。企業から届くスカウトメールの質の高さも一番高いと感じていたので、最終的には『iroots』一本に絞って就活をしていました。
私自身の就活としては、『iroots』で届いた企業からのスカウトメールを見て、興味を持った企業の選考を受けるという進め方でした。ナビサイトで検索して企業を見つけ、エントリーするというのはほとんどやっていません。ただ、そうやって就活に取り組み、いろいろな企業を見ていく中で、徐々に就職をする気持ちになっていきました。就活を通じてさまざまな企業の取り組みやそこで働く人を見ていく中で、自分一人で事業をやっているときより、企業の中で多くの人と協力し、より大きなスケールで物事を見るほうが面白いんじゃないかと感じたんです。こうした経緯から企業への就職を考えるようになりました。
さまざまな領域の社会課題に関わることができ、オーナーシップを持って取り組めることに魅力を感じた
―日本財団からのスカウトを承諾した理由を教えてください。
就職を考えるようになってからさまざまな業界を見ていましたが、その中でも興味を持っていたのがM&A業界です。自分自身が起業をし、いくつかの事業を立ち上げてきた経験から、せっかくつくりあげてきた事業が承継できずに失われてしまうという痛みに共感し、M&A業界に関心を持つようになっていました。そこからM&A業界の企業の選考をメインに受ける中で、大学3年生の終わり頃にとある企業から内定をいただいていたんです。
日本財団からのスカウトメールを受け取ったのは、M&A業界の企業から内定をいただき、就活を終えようとしていたタイミングでした。『iroots』には、気になる企業に対してスカウトリクエストを送信できる機能がありますが、日本財団には過去にリクエストをしていたんです。『iroots』には魅力的な企業が多く掲載されていますが、その中でも日本財団は非営利組織として異色な存在だと感じていました。ですので、実際に日本財団からスカウトメールが送られてきたときには、まずは話を聞いてみようとスカウトを承諾しました。
―スカウト承諾後、選考から内定承諾に至るまでの経緯について教えてください。
先輩から企業の本質は現場の社員と話して初めて分かると聞いていたので、『iroots』でスカウトメールを受け取った企業に関しては、5名以上の社員さんとお話をさせていただいたうえで選考を受けるかどうかを決めていました。日本財団についても、採用担当の方から紹介いただき、いろいろな職員の方と話す機会をつくっていただきました。そこで職員の方々からお話を聞くうちに、すごく面白そうだと感じるようになり、入社できるなら入社したいという気持ちで選考を受けることにしました。
日本財団に興味を持ったポイントはいろいろありますが、特に大きかったのは、扱っている社会課題の領域が非常に幅広いことです。自分自身の性格を考えると、ずっと同じことを繰り返すより、例えば翌年は何をしているか分からないといったように、幅広いプロジェクトに関われるほうが合っていると考えていました。日本財団はさまざまな社会課題と向き合っていますし、個人の意思を尊重してくれるので、自分がやりたいことについてオーナーシップを持って取り組める環境があることが面白そうだと思ったんです。
実際にM&A業界で働いたわけではないのであくまでイメージですが、働いている方々のお話を聞く中で、M&A業界の仕事は成果を上げるための正攻法が決まっていると感じました。企業にアプローチをして、アポイントを取得し、交渉を重ねていくのが一連の流れです。さまざまな企業と出会えますし、企業ごとに課題は異なると思いますが、基本的には正攻法としての進め方の精度をいかに高めていくかが重要になります。一方で日本財団で取り組む社会課題は、明確な解決方法が決まっているわけではありません。課題ごとにアプローチの仕方も変わりますし、プロセスの中で軌道修正することも多いと感じました。より不確実性が高いというのが、自分にとってすごく面白い世界だと思ったんです。

―入社の決め手を教えてください。
スカウトメールを受け取った後にさまざまな職員の方々とお話をさせていただき、入社意欲が高い状態で選考を受けていたので、内定をいただいたときは迷わず入社を決めました。その上で決め手となったポイントを挙げるなら、同じ方向を向いて仕事をしている方が多かったことです。日々さまざまな社会課題と向き合いながら、社会課題を何とか解決したいんだという非常に熱意のある方が多いと感じました。
M&A業界にも事業承継という社会課題を解決しようと働いている方がいる一方で、成果を上げて多くの収入を得たいという方も多かったんですね。それが良い悪いというのではなく、自分が目指したい方向性とはちょっと違うと感じて。日本財団は社会課題の解決を第一において働いている方が多く、より自分に合うと思いました。
さまざまな社会課題の解決に対して興味を持てるような、好奇心旺盛なタイプの方に日本財団は向いている
―入社後、仕事を通じてやりがいを感じていることを教えてください。
現在二つのプロジェクトに取り組んでいますが、その過程で専門家や当事者の方に話を聞きに行く機会が多くあるんですね。お話を伺うことで知らなかった世界がググっと広がるような瞬間があって、知的好奇心が満たされるという意味ですごく楽しいです。
また、NPOや国の方々などいろいろな課題感を持っている方と会話を重ねる中で、例えば「この領域は確かに取り組めていないね」「こうしたらいいかも」など次の展開が見えてくることもあります。そうやって課題を明確にできた喜びや、その課題を何とか解決したいという使命感を持てること、またその課題を解決することで喜んでくれる人がいるだろうと感じられることもこの仕事のやりがいです。
なお、今取り組んでいる課題の一つが、聾児(耳の聞こえない子ども)に対する乳幼児期からの手話言語習得環境の整備です。耳の聞こえない子どもにとってのネイティブな言語は手話となりますが、他の言語と同様、大きくなってからより、0歳から3歳の間に触れることが言語獲得の上では重要です。しかし、こうした環境がまだまだ整備されていません。法整備などは進んでいるものの、まだまだ社会が変わっているわけではないため、こうした状況を何とか変えていきたいとNPOと協力しながら進めています。
取り組んでいる課題のもう一つが、AIを使った自殺対策です。AI活用にはリスクがあるという事例もありますが、防御と活用という側面においては、社会課題解決において新たな可能性もあると言われているんですね。国の動きとしても「自殺対策において人工知能関連技術等の適切な活用を図る」という内容が法律にも明記されていて、今後大きく変わっていく可能性があるんです。ただ、AIを使った相談業務におけるガイドラインはまだ存在していないことから、こうした環境を整備していこうと取り組んでいます。
このように取り組んでいる領域は多岐にわたりますし、非常にスケールの大きなものとなっています。また、私は現在国内事業の担当ですので、国内の団体や日本政府とのやりとりとなりますが、これが海外事業になると、全世界の有識者を巻き込みながら仕事を進めたり、国際会議に出席したりと、仕事のスケールはさらに大きなものとなります。こうした点も日本財団ならではのやりがいと言えるのではないでしょうか。
―日本財団において、今後実現していきたいことを教えてください。
今後取り組んでいきたいことは、孤独孤立対策です。最近では孤独孤立を感じる子どもが増えていますし、分かりやすいところで言えば中高年の孤独孤立も増えています。特に中高年の場合、孤独孤立が自己責任論に終わってしまうなどして、なかなか支援の目が向けられにくい領域だったりします。こうした世の中の風潮を変えていく、支援の必要性を示していくことには大きな関心を持っています。
実は問題が生じているものの、まだ世間的に認知されていないことから、支援の手が差し伸べられていない領域は少なくありません。私はこうした領域にスポットライトを当て、関心を持つ人を増やし、結果的に社会課題の解決につなげる動きを増やしていきたい。最近の例で言えば、ヤングケアラー問題でしょうか。この問題も昔から存在はしていましたが、2016年頃にヤングケアラーという言葉が広く認知されたことで、この領域に対する支援が広まっていったことがありました。このようにスポットライトをいろいろな領域に当てていくことで、まだ認知されていない課題への注目を高めていけたらと思っています。
認知されていないさまざまな社会課題を見つけていくためにも、できるだけ現場へと足を運び、さまざまな人と話すことを大事にしていきたいです。私自身、休日にはNPOが開催するイベントに参加して話をしたり、ソーシャルセクターにいる方に会いに行ったりしています。いろいろなつながりが、その後の活動にプラスになることもありますから。
幸運なる偶然の出会いという意味で「セレンディピティ」という言葉がありますが、そういった出会いは社会課題を解決するうえではすごく大事なものです。だからこそ多くの方に会いに行き、まずは実際に話してみるということを今後も心がけていきたいです。
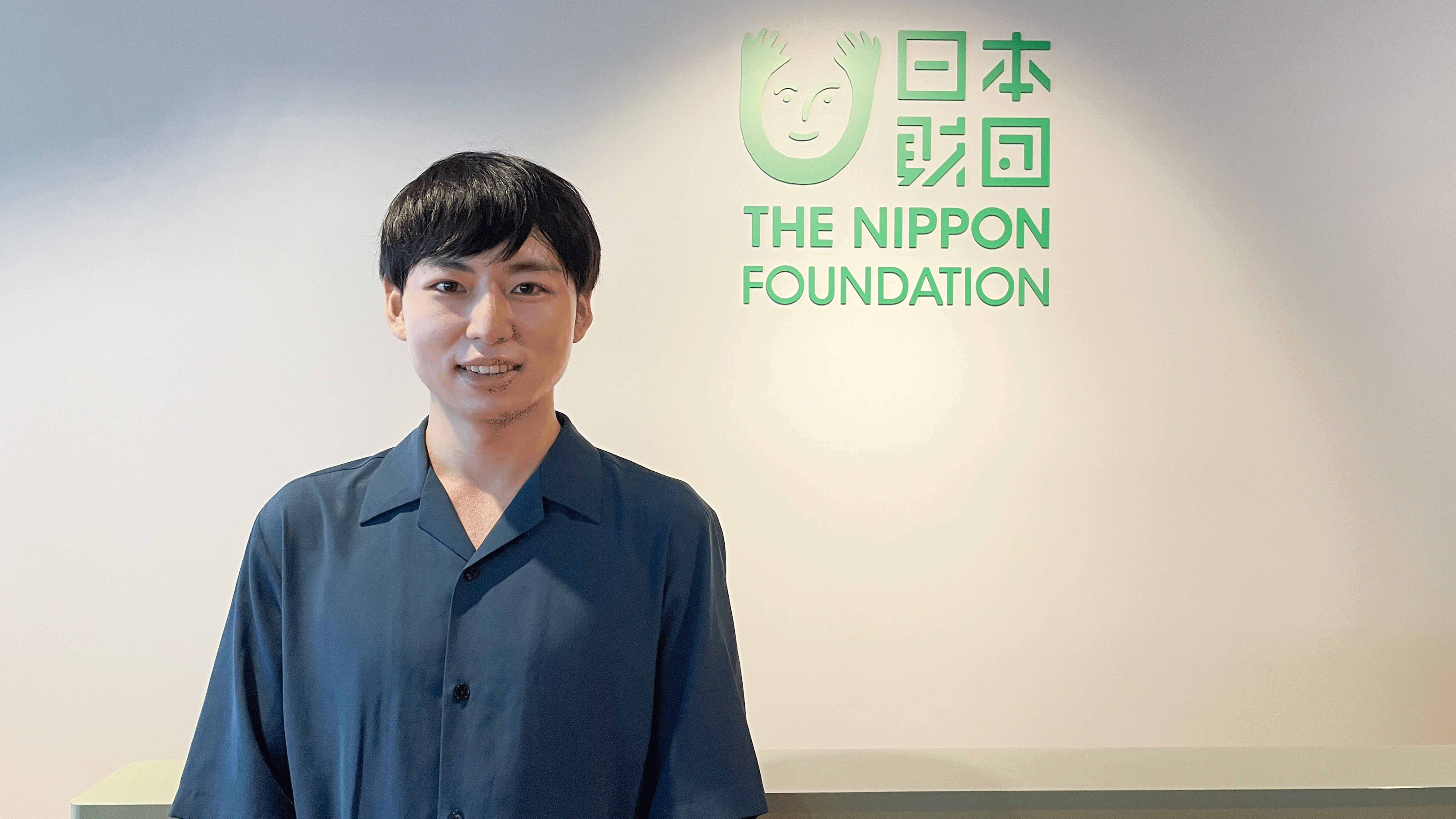
―最後に、irootsユーザーへのメッセージをお願いします。
日本財団では、非常に幅広い分野に関わることができます。一つの業界の企業で働くことと比較すると、非常に幅広い領域の社会課題に関わることができると感じています。さらに、仕事のスケールも非常に大きいです。営利組織ではなく非営利組織で働くというのも貴重な経験となるのではないでしょうか。お金を稼ぐ組織ではなく、お金を使わせてもらう組織で働くということは、なかなかない経験です。利益よりもまず課題解決を先行して考えるという点で、社会を変えていくことに本気で取り組める環境だと思います。
そんな組織だからこそ、社会課題の解決に本気で取り組む人たちと一緒に、同じ方向性を向いて働くことができるのも大きな魅力。職員数も150名程度と多くありませんので、一人ひとりがオーナーシップを持って取り組める組織であることもお伝えしたいと思います。私自身も、入社後早い段階から裁量のある仕事を任せてもらい、社会課題の解決に向けて取り組めることをやりがいに感じています。
一方で、日本財団はあくまで助成財団であることもお伝えしておきたいです。現場の第一線で支援の必要な当事者と直接関わる仕事ではなく、NPOなど社会課題と向き合う方々を支援し、より大きなインパクトを残せるよう後方支援や全体の管理をするのが私たちの役割です。話を聞きに行くことは多くありますが、現場に張りついて働くのではなく、全体を俯瞰しながらサポートする存在であることを理解していただけたらと思います。
こうした点から、一つの領域や特定の社会課題に強い興味がある方より、さまざまな社会課題に幅広く興味を持てる方に向いています。あらゆる領域のことに対して何でも興味を持てるタイプの方であれば、日本財団ではやりがいを持って働けると思います。