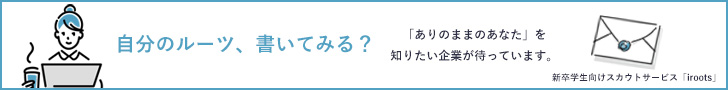脱・ゆるブラック。「仕事はラクだが、力がつかない」「自分の市場価値に自信が持てない」…そんな悩みを抱えるのではなく、“ラクではないが力がついた”と胸を張れる人になりたい。そんな想いを胸に、ラクではないが力がつく環境=「若手ホワイト企業」で奮闘する若手社員の経験にフォーカスし、自分の力でキャリアを切り拓くためのエッセンスを紐解く。
●若手ホワイト企業とは?
新卒スカウトサービス『iroots』では、会社の評判プラットフォーム「エンゲージ 会社の評判」に寄せられた口コミの中から「20代の成長環境」と「実力主義」のスコアにフォーカスし、“ラクではないが力がつく”企業を「若手ホワイト企業」と認定。>>若手ホワイト企業について詳しく知る
Interviewee’s Profile
設立:1983年9月 従業員数:1,654名
東京海上グループのIT・デジタル戦略の中核を担うユーザー系SIer企業。東京海上日動の『バリューパートナー』として、既存ビジネス領域と新規ビジネス領域の両方を支援。「お客様や地域社会の“いざ”をお守りする」というパーパスを実現するために、DXによる変革に挑んでいる。
塚本 旬哉 損害本部 損害システムデザイン部所属 エンジニア
2022年に新卒で入社後、東京海上グループで利用される基幹システムやスマホアプリの開発、保守・運用に従事。業務の傍ら、基本情報技術者、応用情報技術者、AWSソリューションアーキテクトの資格を取得。
- 社会への影響度の高い、大規模なシステム開発に関わりたかった
- 1年目からグループ内の基幹システムの開発に参加。若手のうちから、責任ある仕事を任される環境
- 「ユーザーにとって、より良いシステムは何か」を追求できるエンジニアへ
TOPICS
社会への影響度の高い、大規模なシステム開発に関わりたかった

―最初に、東京海上日動システムズに入社を決めるまでの経緯について教えてください。就活をはじめたときには、どのような軸で企業選びをおこなっていましたか。
大学では理学部で宇宙や地球内部のことを研究していたのですが、どうしても就職先が限られてくるので、専門分野はこだわらずに就職活動をしました。そこで将来的にスキルがしっかりと身につき、活躍し続けられる環境として考えたのがIT業界です。IT業界は人材不足と聞いていましたし、求人募集も多かったので、プログラミングスキルを身につければどこの企業でも活躍できるのではと考えました。それに加え、自分が携わったものについて自信を持って相手に話せるというのも、ITの仕事に惹かれた部分でした。
その中でも大企業は、大規模なシステムに関わるチャンスもありそうですし、社会への影響度も高いので、自分の志向性に合いそうだと感じました。特に保険ビジネスは多くの保険ご契約者様の安心につながるサービスで、損害保険のリーディングカンパニーである東京海上日動のシステム開発に携わることは、世の中への貢献につながると思ったんです。
―その中で、東京海上日動システムズに興味を持ったきっかけを教えてください。
最初に東京海上日動システムズを知ったのは、大学3年生の夏頃です。就職活動を支援してくれる方の紹介で、当社を教えてもらいました。東京海上グループの、IT・デジタル戦略の中核を担っていると聞き、興味を持ったのがきっかけです。
まず半日の体験ワークショップに参加したのですが、保険業界は安定したサービスを提供する必要性があるため、経営基盤が堅固であるという部分に魅力を感じました。ITエンジニアとして成長していくためには長期的なキャリアを描けることが重要だと感じていたので、この会社であればITエンジニアとしてのスキルをしっかりと身につけられるのではないかと思いました。また、福利厚生も充実していて、休日も多く、柔軟に働けると感じたのも魅力のひとつです。
その後、先輩社員との座談会やオンラインの職場見学などを通じて、若手の先輩社員がフラットに会話している様子に魅力を感じました。上司や先輩も誰に対しても「さん付け」で呼び合っていたり、何かあったらすぐ相談できそうな雰囲気を感じたりしたことから、自分の性格にも合っているのではないかと感じたことを覚えています。
―選考を経て、東京海上日動システムズに入社を決めた理由を教えてください。
実はほかにも1社、ユーザー系SIer企業から内定をいただいていたのですが、どちらの会社に入社するかは非常に悩みました。ただ、自分の就職軸を振り返ったときに、より将来性のある経営や事業を行なっている会社のほうが、ITエンジニアとして力がつくのではないか、と考えたことが決め手になりました。保険は私たちの生活に欠かせないものであり、そのシステム基盤をつくっていく仕事なら、若手のうちから多くのことを学び、成長していけるのではないかと思い、最終的に東京海上日動システムズへの入社を決めました。
1年目からグループ内の基幹システムの開発に参加。若手のうちから、責任ある仕事を任される環境
―2022年にご入社されてから、今までどのような業務に携わられましたか。
入社後は半年間、集合研修があり、1ヶ月ほどビジネススキルを学び、その後は約2ヶ月間、Javaのプログラミング研修を受講しました。そのあとは研修の集大成の総合演習で、9月までチームでシステム開発の実技研修を行ない、10月から正式配属になりました。
配属後、最初に担当したのは、グループ社員が利用する基幹システムのバージョンアップに関する開発プロジェクトです。2年目の6月にリリースしてからは、障害対応や保守・運用を担当し、現在は並行してスマホアプリ開発にも携わっています。
業務を進めていく上で、上司や先輩からのアドバイスに助けられることも多いですが、自主的な勉強も欠かさないことで、ITエンジニアとしての成長を実感しています。切磋琢磨できる同期が多いのも、刺激になっています。

「ユーザーにとって、より良いシステムは何か」を追求できるエンジニアへ
―入社してから今までの間に「ラクではないが力がついた」と思う経験を教えてください。
配属してから2ヵ月目に担当した、基幹システムのバージョンアップ業務が一番記憶に残っています。基幹システムのバージョンアップ対応ということで、会社をあげての一大プロジェクトでした。保険金の支払いなどに関わるシステムなので、大規模かつミスが許されず、プレッシャーを感じながら開発を進めました。
当時はまだ社会人1年目で、研修を受けたとはいえ保険の知識が浅く、エンジニアとしての技術も足りていない状態でした。そこで意識したのは、自分で調べるだけではなく、上司や先輩に質問したり、相談したりすることです。みなさん多忙な中で時間をとってくれるので、事前に質問や相談したい要点を整理して、負担を少しでも減らせるよう意識しました。上司や先輩から受けたアドバイスを実行して、また不明点が出てきたら質問して……ということを3ヶ月くらい繰り返したところ、だんだん話にもついていけるようになり、報・連・相のスキルも上がったと感じています。
繰り返しにはなるのですが、保険業界のシステムは「ミスがなくて当然」のものなので、慎重に開発を進める必要があります。ですから、「相談に時間をとらせて申し訳ない」と考えるのではなく、よりよいサービス品質を追求するためには必要な時間なんだ、と認識することが大事だと考え、積極的に質問、相談するようになりました。
―得られた経験をもとに、塚本さんは今後どのようなキャリアを歩んでいきたいですか。
ユーザーの要件や仕様を満たすシステムを開発するのはもちろんのこと、今後は未来の保険会社の在り方を踏まえながら、「ユーザーにとって、より良いシステムは何か」という広い視点を持って、ITエンジニアとして成長していきたいと思っています。システムを利用する東京海上グループのみなさん、そしてその先にいらっしゃる保険ご契約者様の方々にもっと貢献できるITエンジニアになりたいです。
技術的な部分でいうと、社内の教育環境が整っているので、IT未経験者でも学ぼうとする高い意欲があれば、スキルアップの機会が沢山あります。『Udemy』というオンライン学習プラットフォームも導入されていて、社員一人ひとりが学ぶことに関して応えられる環境ですから、ITエンジニアとして中長期的に成長できると感じています。実際、私も入社後に基本情報技術者、応用情報技術者、AWSソリューションアーキテクトの資格を取得することができました。
これからも保険という社会的意義の高いサービスを支える存在として、東京海上グループ内で頼られるITエンジニアになっていきたいです。
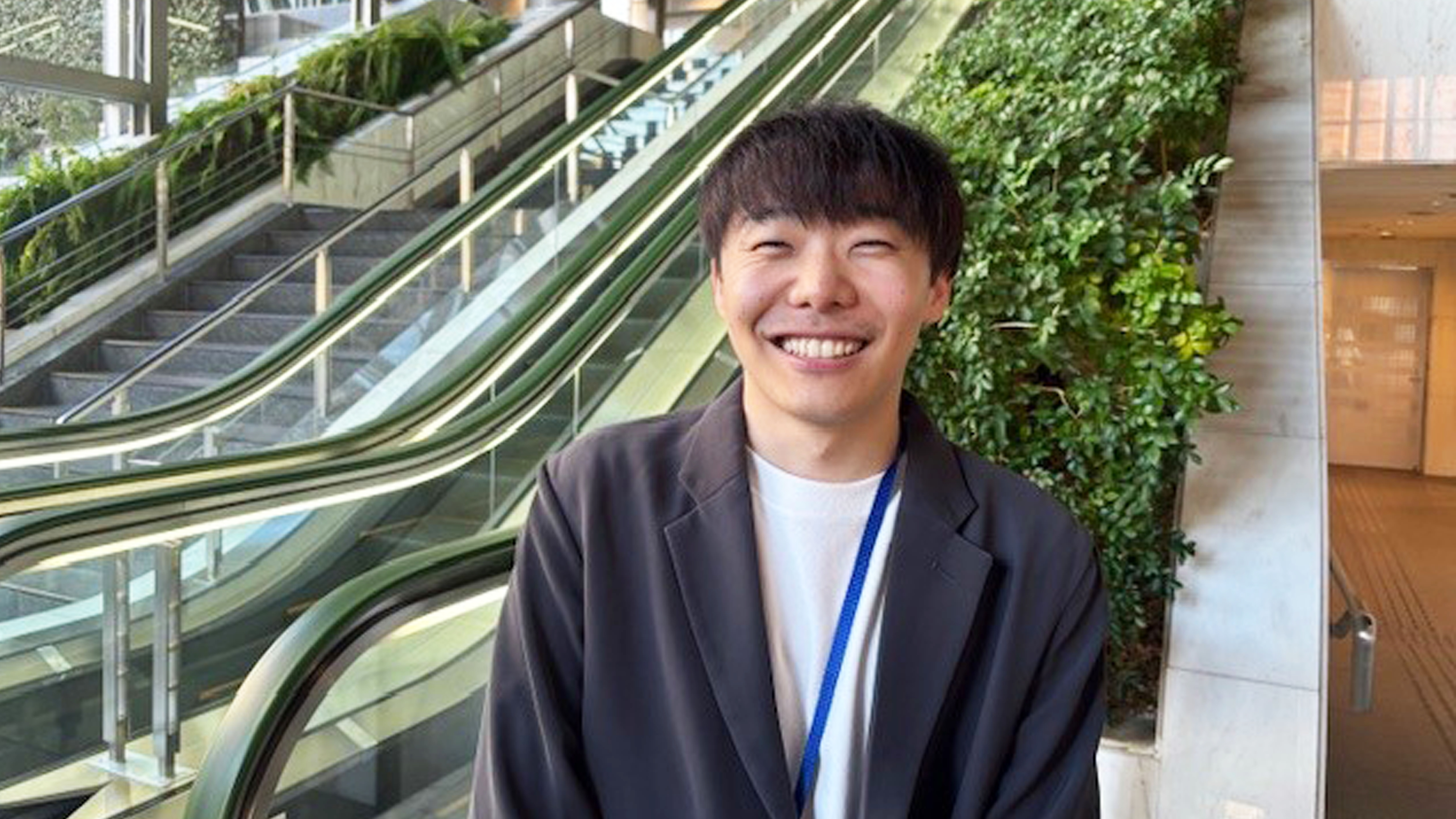
・東京海上グループの一員として、保険サービスを支える「社会貢献性」
・入社1年目から大規模プロジェクトに参加する機会がある「20代の活躍環境」
・仕事やキャリアのことを上司・先輩に相談しやすい「風通しの良さ」