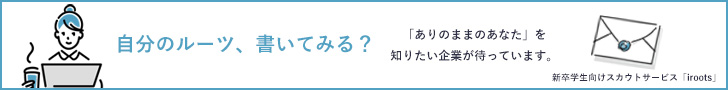脱・ゆるブラック。「仕事はラクだが、力がつかない」「自分の市場価値に自信が持てない」…そんな悩みを抱えるのではなく、“ラクではないが力がついた”と胸を張れる人になりたい。そんな想いを胸に、ラクではないが力がつく環境=「若手ホワイト企業」で奮闘する若手社員の経験にフォーカスし、自分の力でキャリアを切り拓くためのエッセンスを紐解く。
●若手ホワイト企業とは?
新卒スカウトサービス『iroots』では、会社の評判プラットフォーム「エンゲージ 会社の評判」に寄せられた口コミの中から「20代の成長環境」と「実力主義」のスコアにフォーカスし、“ラクではないが力がつく”企業を「若手ホワイト企業」と認定。>>若手ホワイト企業について詳しく知る
Interviewee’s Profile
設立:1920年 従業員数:2万8111名(2024年3月末現在 ※単体)
データとテクノロジーでサステナブルな社会を実現する社会イノベーション事業を推進している企業。特に今回フォーカスする公共システム事業部・公共システム営業統括本部では、官公庁、自治体、研究・教育機関、道路や消防分野など公共分野のお客様を、ITの側面から50年以上にわたって支援している。
羽賀 隼平(はが しゅんぺい)公共システム営業統括本部
京都大学文学部を卒業後、2022年4月に株式会社日立製作所に新卒入社。公共システム営業統括本部にて、官公庁担当としてさまざまなシステムの企画・設計・運用などを支援している。趣味の卓球は中学校から本格的にスタートし、大学では体育会卓球部の主将として40-50名をマネジメントしていた。
- 提供するソリューションの幅広さを知り、日立製作所なら社会課題の解決ができると思った
- 公共システム営業統括本部の官公庁担当として、国民が使用するシステムの提案・導入に関わっている
- 幅広い経験が詰める日立グループで、金融や産業など公共以外の領域にもチャレンジしていきたい
TOPICS
提供するソリューションの幅広さを知り、日立製作所なら社会課題の解決ができると思った
―最初に、日立製作所に入社を決めるまでの経緯について教えてください。就活をはじめたときには、どのような軸で企業選びをおこなっていましたか。
就活をはじめたのは、大学3年生の春くらい。就活に重きを置いていたわけではないのですが、新型コロナウイルス感染症の影響から授業がリモートになり、部活動もできなくなったことからはじめることにしました。そんな温度感でのスタートだったので、大学3年生の夏のインターンのタイミングでは、特に就活の軸はありませんでした。興味を持った企業のインターンの募集に順番に応募していった形です。
最終的に応募したのは20社くらい。ITからメーカー、コンサル、不動産まで業界はさまざまでしたが、職種は営業職、もしくはそこに近しい職種をメインに応募していました。
営業職を志望するようになったのは、就活をはじめてから取り組んだ自己分析の結果です。体育会の卓球部にて、チームのみんなで一つの目標に取り組んでいくことにやりがいを感じていて、営業職なら同じようなやりがいを味わえそうだと考えました。また、卓球部の主将としてチームを率いた経験があったことから、自分が旗を振りながらチームを方向づけていける仕事や会社に魅力を感じるようになっていきました。
―その中で、日立製作所に興味を持ったきっかけを教えてください。
日立製作所と出会ったのは大学3年生の秋くらい、夏のインターンへの参加がひと段落した頃です。インターンへの参加を通じてIT業界への関心が高まり、いろいろな企業を見ていく中でたまたま出会いました。もちろん会社のことは知っていましたが、改めて会社について調べてみて、グループ会社を含めて幅広いソリューションを提供していることを知り、この会社ならお客様に広く価値提供できると感じましたね。
当時は、公共事業の領域に強い興味があったわけではありませんでした。ただ、日立製作所が提供しているソリューションの幅広さに加え、大規模な事業再編や新しい人事制度の採用など変化を恐れない社風に惹かれ、この会社ならさまざまな手段で社会の課題解決ができるんじゃないかと強く惹かれたのを覚えています。こうした背景から、日立製作所の選考を受けることにしました。

公共システム営業統括本部の官公庁担当として、国民が使用するシステムの提案・導入に関わっている
―選考を経て、日立製作所に入社を決めた理由を教えてください。
日立製作所の選考は、営業職コースでエントリーしました。最終的に入社を決めた理由はたくさんあるのですが、ここでは特に決め手となったポイントをいくつか紹介します。
一つ目は、チームの旗振り役となって大きなプロジェクトを動かしていけると感じたことです。選考過程ではさまざまな職種の方々にお会いしました。営業やシステムエンジニアの方々からお話を伺う中で、社会を支える大規模システムに関わる日立製作所の営業であれば、社内外問わず様々なメンバーを巻き込みながら、大きなプロジェクトを進めていけると感じられたことに強く惹かれました。
続いて二つ目は、入社1年目、2年目など若いうちから責任ある仕事を任せてもらえると感じたことです。日立製作所のような大手企業の場合、早い段階ではあまり任せてもらえないイメージを持っていたんですね。しかし、社員の方々から「入社後先輩社員から1対1でサポートいただけるメンター制度」や「若手のうちから主体的に提案し、受注に繋げた体験談」を伺い、自分も早い段階からチャンスを掴めるのではないかと感じたんです。
そして三つ目が、日立製作所の社会への影響力の大きさです。日立製作所にはさまざまなビジネスユニットがあり、それぞれのビジネスユニットが、IT×OT×プロダクトに代表される多種多様な技術を基盤とした幅広いソリューションを武器に、多面的に、お客様・社会の課題にアプローチをすることができます。そういったお話を具体的にお伺いすることができ、自分もそんな仕事がしたいと思ったことが決め手になりました。
ちなみに、社員の方々には面談や面接の際にお会いしたのですが、お会いした方みなさんが「一緒に働きたい!」と思える魅力的な方々ばかりだったのも印象に残っています。自分らしくのびのび働き、自分なりのキャリアを描いている先輩たちと話すことで、ここなら思い描くキャリアを実現できそうだと感じましたね。
―2022年にご入社されてから、今までどのような業務に携わられましたか。
入社後は公共システム営業統括本部への配属となり、4年目の現在も同じ部署に在籍しています。最初の3ヶ月くらいは研修期間でしたが、大学時代の友人が入社した他の会社と比較して、期間も内容もかなり手厚いと感じました。現場でも先輩に教わりながら進められますので安心してスタートをきれました。
配属後は、主に官公庁を担当しています。担当するシステムはさまざまで、官公庁の職員が業務で使用する内部のシステムもあれば、私たち国民が使用する外部向けのシステムもあります。特に国民が日常的に使用するシステムの場合、システムエラーなどで止まってしまうことが絶対にあってはなりません。多くの人々が使用しているというプレッシャーもありますが、国民生活を支えていると感じられるのは大きなやりがいです。
プロジェクトが長期に及ぶというのはこの仕事の特徴です。まずはお客様のもとへこまめに足を運び、職員の方々が何に困っているのか、システムユーザーである国民からどんな声が届けられているかをヒアリングするところからスタート。現状や課題が把握できたら、課題に沿って解決策を提案していきます。
一般的な企業であれば提案後に受注となるかもしれませんが、官公庁の場合は税金の中から予算を確保し、入札をして決定という流れになっています。そこから受注できればシステムを構築、稼働と移っていきますが、長期のプロジェクトだと数年間にも及ぶものも。実際、私が先輩から引き継いだ案件で5年ほどかかったものもあります。だからこそ、プロジェクトが終了したときには大きな達成感を味わえます。
私がいる公共システム営業統括本部に限らず、日立製作所全体で考えたときでも、社会貢献性の高い仕事ができる環境ですね。日々の仕事において、自分が担当するお客様の課題を解決するのはもちろんですが、上司や先輩から「この課題に取り組むことで、日本の社会課題をどう解決できるのか?」とよく聞かれるんです。こうしたやりとりが普段の会話でも出てくるくらい、広い視点で仕事に取り組めるのが、醍醐味の一つです。
それに加えて、さまざまな課題に対し、日立製作所の枠に留まらず、日立グループ全体の力や、社会課題解決に向け、社外の方々とも協創しながら、幅広いソリューションを提供していけるのも大きな特徴。自分の提案によってお客様に喜んでいただけるだけでなく、日本の社会課題解決にもつながっていく。大きなスケールで社会貢献を感じられる仕事だと思いますね。

幅広い経験が詰める日立グループで、金融や産業など公共以外の領域にもチャレンジしていきたい
―入社してから今までの間に「ラクではないが力がついた」と思う経験を教えてください。
入社4年目を迎えますが、毎年成長できていると感じます。私は文学部出身で、プログラミングのことも分からなかったので、必死に学ぶところからのスタートでした。特に1年目は右も左も分からずでしたが、知識が増えることでできることも増えていき、徐々に自分は社会をこう変えていきたいという気持ちが芽生えていきました。
例えばお客様から何か依頼されたときでも、ただそれに応えるだけでなく、「お客様は本当はこういった情報を求めているんじゃないか?」「こうしたら進めやすいんじゃないか?」と逆算したうえで取り組むようにしました。そうやって試行錯誤を繰り返すことで、考える習慣を身につけていきました。
1年目の終わり頃にはメイン担当としてお客様を持つようになり、3年目の半ばくらいには自分が主体となってプロジェクトを動かせた経験もできました。プレ活動と言われるお客様の課題をヒアリングし、その課題に対して日立製作所の幅広いソリューションの中から何ができるかを考える。お客様である官公庁にも何度も足を運び、社内各部署との調整や連携も密に進めていく。こうした一連の流れを中心メンバーとして進めていくのが営業の役割です。自分が立てた戦略がうまくいって受注につながったときはすごく嬉しく思いますし、最終的にお客様に感謝の言葉をいただけたときはたまらない気持ちになるんですよ。
―得られた経験をもとに、羽賀さんは今後どのようなキャリアを歩んでいきたいですか。
短期的な目標で言えば、これまでの経験をもとに他の省庁など新しいお客様を担当したり、新しいシステムや新しい分野に挑戦したりと、これまでやったことがないことに取り組んでみたいです。長期的な視点で考えると、公共システム営業統括本部でさらに経験やスキルを磨いたうえで、ゆくゆくは金融や産業など公共以外の領域にもチャレンジしてみたいです。自分自身が公共分野で学んだこと、身につけたことを活かして、他の領域でも自分がどれだけできるのか力試しをしたいと思っています。
日立製作所という大きな組織だと、若手にはなかなかチャンスがないと思うかもしれません。しかし実際には、入社1年目、2年目から責任ある仕事を任せてもらい、社会にインパクトのある仕事をすることができます。また、日立グループならではの幅広いソリューションを提供できるのも大きな特徴です。社会に貢献したい、世の中の役に立ちたいと考えている学生の方がいたらぜひオススメしたいですね。

・ 国民生活を支え、日本の社会課題解決につながる「社会貢献性」
・入社1年目から、社会にインパクトを与える仕事に挑戦できる「20代の活躍環境」
・役職に関わらず本質的な議論ができる、オープンな「風通しの良さ」