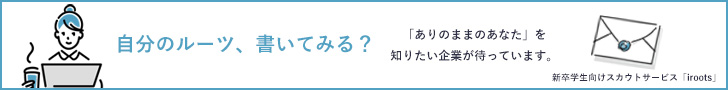脱・ゆるブラック。「仕事はラクだが、力がつかない」「自分の市場価値に自信が持てない」…そんな悩みを抱えるのではなく、“ラクではないが力がついた”と胸を張れる人になりたい。そんな想いを胸に、ラクではないが力がつく環境=「若手ホワイト企業」で奮闘する若手社員の経験にフォーカスし、自分の力でキャリアを切り拓くためのエッセンスを紐解く。
●若手ホワイト企業とは?
新卒スカウトサービス『iroots』では、会社の評判プラットフォーム「エンゲージ 会社の評判」に寄せられた口コミの中から「20代の成長環境」と「実力主義」のスコアにフォーカスし、“ラクではないが力がつく”企業を「若手ホワイト企業」と認定。>>若手ホワイト企業について詳しく知る
Interviewee’s Profile
創業:2018年2月、従業員数:210名(連結、2025年6月末時点)
「次世代の人々が地球を理解し、レジリエントな未来を実現するための新たなインフラをつくる」というビジョンを掲げ、宇宙から得られるデータと最先端の解析技術を駆使して社会課題の解決に取り組んでいる。主な事業内容は、小型SAR衛星と関連システムの開発・製造・打ち上げを通じた衛星コンステレーションの運用と、その取得データの販売、そしてデータ解析ソリューションの開発・販売など。
遠藤 幸夫(えんどう ゆきお)ソリューション開発部/InSARアナリティクスユニット/マネージャー
東北大学大学院 修士課程を修了後、2020年4月に株式会社Synspectiveに新卒入社。大学では土木工学を専攻しており、人工衛星を使って災害被害を把握する研究をしていたことから同社の事業内容に興味を持って入社を決めた。修士1年夏から2年夏までの約1年間、アメリカ・ワシントン大学に留学もしていた。
- 大学での研究を、社会に役立てる技術へ。人工衛星に関連する仕事ができることから、Synspectiveへの入社を決めた
- 入社4年目でマネージャーへと昇格し、6年目から二つのプロダクトのテックオーナーとして活躍
- プロダクトの技術面だけでなく、売上やユーザーエクスペリエンスまで考えるプロダクトオーナーへと成長していきたい
TOPICS
大学での研究を、社会に役立てる技術へ。人工衛星に関連する仕事ができることから、Synspectiveへの入社を決めた
―最初に、Synspectiveに入社を決めるまでの経緯について教えてください。就活をはじめたときには、どのような軸で企業選びをおこなっていましたか。
大学時代は就活をせず、大学院修士課程で研究を続けていました。修了後はそのまま博士課程に進んでも良いかなと考えつつも、人工衛星の社会実装にも興味があり、企業に就職し、人工衛星がどう活用されているかを勉強するのも面白いかなと考えていました。
それぞれの進路で考えると、大学院で研究を続けた場合、やりたい研究をとことん深掘りでき、一つの分野に詳しくなれるのが魅力でした。企業で働く場合には、やりたいやりたくないに関わらずさまざまなプロジェクトに関わり、新たな能力を開発していけるだろうと。どちらの進路も魅力だったため、絶対に就職すると進路を絞ったわけではなく、社会人になっても人工衛星に関連した仕事ができる企業を探していました。
ちなみに私は、修士1年の夏から1年間アメリカに留学していたので、日本の一般的な就活スケジュールには乗っていなかったんですね。そんな背景もあり、企業を探す際はちょっと特殊かもしれませんが、海外サイトで情報収集をするという方法をとっていました。
日本の就職ナビサイトだと、基本的に一括採用ということもあり、仕事内容などは詳しく記載されていません。しかし海外サイトであれば、ジョブディスクリプション(職務記述書)に仕事内容や求めるスキルが詳しく記載されています。例えば「Pythonで○○ができるのが必須条件です」「この言語とこの言語を使えるのが歓迎条件です」「こんな画像の解析をする仕事です」など、必須や歓迎の条件が書かれているわけです。留学をしていて英語に抵抗がなかったのもありますが、どんなミッションを担い、どんなスキルが必要か分かりやすいからこそ、自分にできそうか、やりたいかどうかも判断しやすかったと思っています。
―その中で、Synspectiveに興味を持ったきっかけを教えてください。
修士2年の夏、海外留学から帰ってきた際は、大学で研究を続けるのと企業に就職するのは半々くらいの気持ちでした。しかしそのタイミングで、Synspectiveが宇宙セミナーを開催する話を聞き、社名も聞いたことがあるし参加してみようかなと興味を持ちました。
セミナーに参加したところ人事担当者と仲良くなり、会社の話をいろいろ聞かせてもらったり、オフィス見学をさせてもらったりしました。社長や役員ともお話をする機会をいただいたことで、面白い会社だと感じたんですね。タイミングが良かったのでしょう。面白い会社と出会い、社員の方々とも仲良くなるという過程がトントン拍子に進んでいったことから、これも何かの縁だと入社したいという気持ちが強くなっていきました。
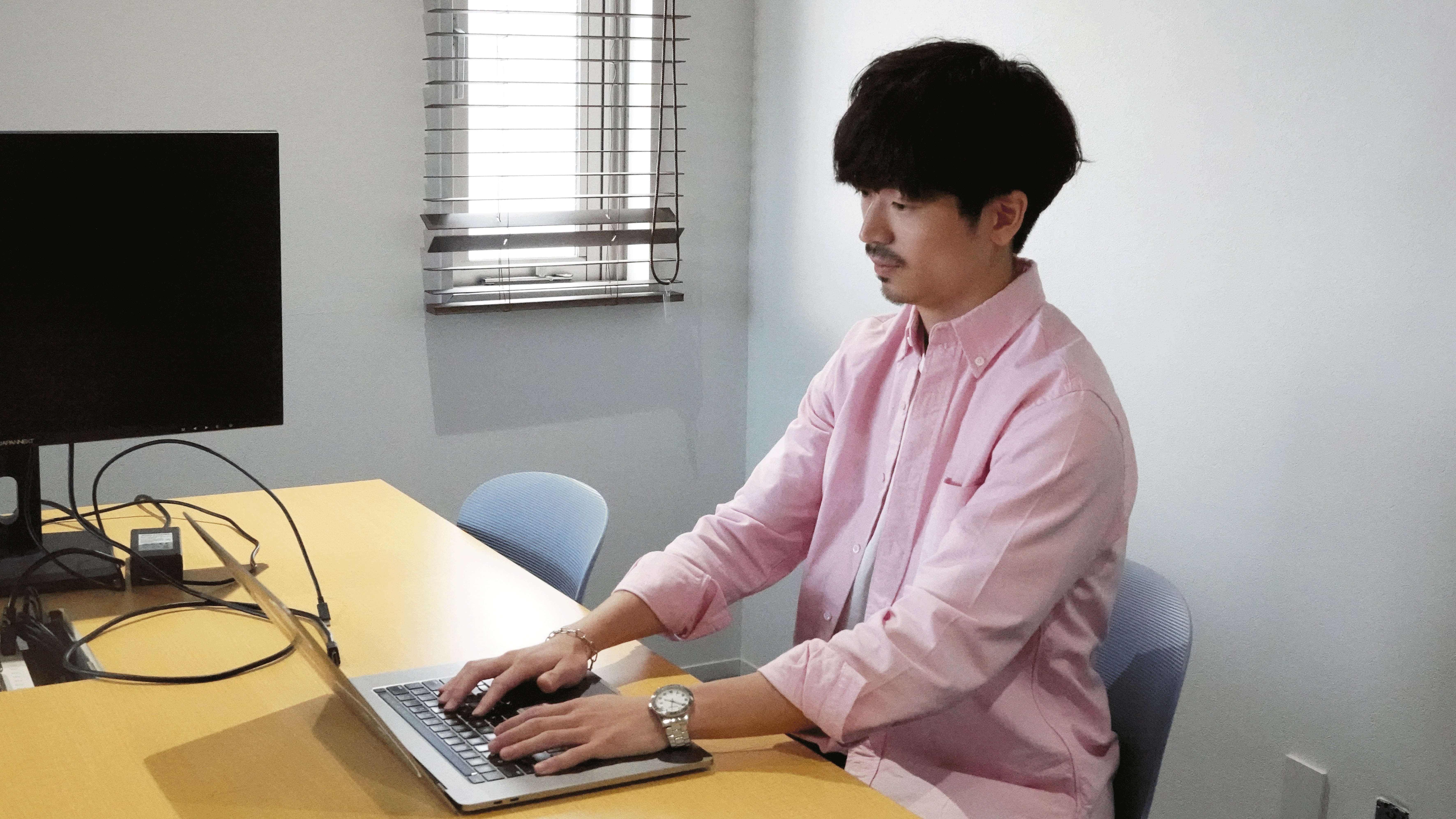
入社4年目でマネージャーへと昇格し、6年目から二つのプロダクトのテックオーナーとして活躍
―選考を経て、Synspectiveに入社を決めた理由を教えてください。
入社の決め手は、会社に興味を持ったポイントと基本的に同じです。人工衛星に関連する仕事という自分がやりたいことができることと、将来性を感じたこと。Synspectiveが掲げるビジョンにも共感し、どんなプロジェクトに関わるとしても面白そうだと感じたんです。
それ以外で魅力に感じたのは、外国人スタッフが多く活躍している組織だったこと。日本人だけでなくさまざまな国のエンジニアと働き、一緒に良いプロダクトを開発していくというのは非常に魅力的でした。自分が海外留学をしていたこともあり、さまざまな国籍、さまざまな価値観を持つメンバーと一緒に働けることは刺激的で面白そうだと思ったんです。当時のSynspectiveは新卒採用をしていませんでしたが、特に不安はありませんでした。それ以上に、やりたいことができる会社に入社できてラッキーという気持ちが大きかったです。
―2020年にご入社されてから、今までどのような業務に携わられましたか。
入社した当時は新卒採用を実施していませんでしたが、研究室と比較しても、想像以上に手厚いサポート体制があると感じました。入社した社員にいろいろ教えるのはどの会社でもやっていることですが、例えば「このツールはこう使ってね」「分からないことがあれば何でも聞いてね」など、すごく丁寧に教えていただきました。
そこから現在までに、大きく分けて二つのプロジェクトに関わってきました。最初に関わったのが、小型SAR衛星の画像やその他の衛星データを用いて地盤の沈下や変動を把握するというプロダクト。最初の2年くらいは機能開発に携わり、徐々にプロダクトのテックオーナー的な役割を担い、どんな機能を開発するかを考えたり、各機能開発をメンバーにアサインするようになりました。入社4年目からは正式にマネージャーへと昇格しています。
入社6年目からは、小型SAR衛星によって広域の地表面を観測し、その画像から浸水被害を解析するプロダクトのテックオーナー的役割を担っています。キャリアを振り返ると、前半は自分の手を動かして開発する仕事が多くて、中盤からプロダクトのテックオーナーを担うようになりました。
大学での研究と今の仕事を比較すると、研究ではすごく細かく条件を定めて解析を行い、解析結果が出た要因を追究していく、つまり一つの問題を深掘りしていくイメージでした。一方で仕事でのプロダクト開発では、あらゆる問題に対して優先度をつけ、より汎用性の高い問題に対してアプローチをしていくのだと感じました。どちらが良い悪いというのではなく、目的が違うからこそ取り組み方も異なるのだと理解しています。
また、研究室で解析を行う際は基本的に一人でプログラミングのコードを書いていたのに対し、仕事でのプロダクト開発では多くのエンジニアでコードを共有しながら開発に取り組みます。コードの書き方には人それぞれスタイルや哲学がありますが、それらを理解したうえで、他の人が書いたコードに修正をしたり、新たな提案をしたりというのは研究室ではなかった経験だったので新鮮でした。多くのエンジニアでコードを共有し、歩調を合わせながら開発を進めていくというのは慣れるまではちょっと大変でしたね。
こうした環境で仕事を進めていくにあたり、入社してから意識していたことがあります。それは会議などエンジニアが集まる場で、自分から積極的に質問することで、自分と相手が考えているポイントがどれくらい違うのかを確認していたことです。例えば「○○の問題が発生したらどう対処しますか?」と質問すれば、その問題をそもそも認識していたのか、認識していたらどう対処するかを知ることができます。そうすることで、実際に問題が起こったときもスムーズに解決できるからです。質問して言語化をすることで、相手と同じ景色を見ることができるようにする。研究と違って大勢のメンバーが関わってプロダクトを開発していくからこそ、認識のズレが生じないようにすることを意識していました。
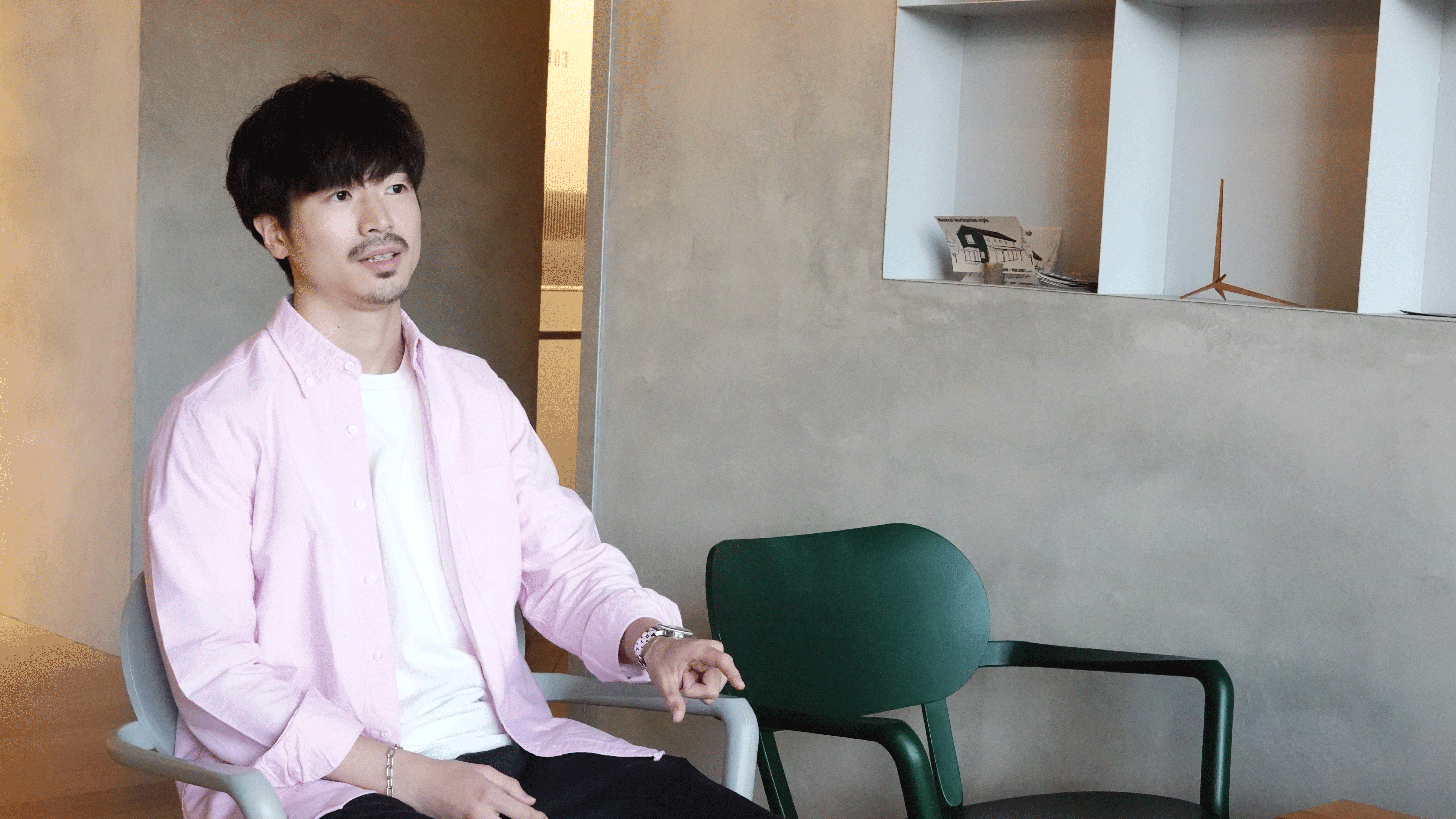
プロダクトの技術面だけでなく、売上やユーザーエクスペリエンスまで考えるプロダクトオーナーへと成長していきたい
―入社してから今までの間に「ラクではないが力がついた」と思う経験を教えてください。
入社6年目になって、小型SAR衛星で浸水被害を把握するプロダクトのテックオーナーを新たに任されたときです。これまで担当していた地盤沈下を把握するプロジェクトは、最初に機能開発からスタートし、徐々にテックオーナー的な役割も任されるようになるなど、プロダクトの理解を深めながら段階的に役割が広がっていきました。マネジメントについても関係性が築けているメンバーを任せてもらっていました。
しかしこのときは、今まで関わっていなかったプロダクトをいきなり担当することになりました。どんなステークホルダーがどう関わっているかも分かりませんし、どんな思想、どんな経緯で今のプロダクトになっているかも最初は知らないわけです。メンバーとの関係性もイチから築いていくことになります。こうした状況下で、プロダクトを短期間で把握し、新たに意思決定していくのは容易ではありませんでした。
こうした中で大事にしていたのが二つのポイントです。一つは、そのプロダクトにどんな人がどう関わっているのかを正しく把握すること。例えば事前に情報を聞いていても、実態としては全く違う人がプロダクト開発に多大なる貢献をしていることもあります。外部から見た情報、周囲から聞いた情報と実態が違うこともありますので、自分の目で見て耳で聞いて、正しく実情を把握することが重要だと感じました。
もう一つは、プロダクトに合わせた開発スケジュールの管理を行ったことです。浸水被害を把握するプロダクトは、いつまでに何を開発するかという計画を細かく決めていたんですね。もともと担当していたプロダクトとは進め方が異なったのですが、細かくスケジュールを管理するやり方を知り、テックオーナーは全体の方針を決めるだけでなく、プロダクトに関わるメンバーが気持ちよく仕事ができるようにすることが大事だと考えるようになりました。こうした経験から自分の引き出しも増えたように思います。
―得られた経験をもとに、遠藤さんは今後どのようなキャリアを歩んでいきたいですか。
現在、地盤沈下の解析と浸水被害の把握という二つのプロダクトのテックオーナーを担当していますが、今後は技術的なところだけでなく、実際にどうやって売上を伸ばしていくのか、どういったユーザーエクスペリエンスを提供していくのかなど、より上位の概念から考えられるようになっていきたいと思っています。
例えばどういった機能があれば売上が伸びるのかなど、ビジネス的な視点も含めてプロダクトをどう開発していくのかを考える。テックオーナーからプロダクトオーナーへと成長していくと言いますか、自分が関わることができる範囲をさらに広げていきたいです。
学生のみなさんにSynspectiveを勧めるなら、まだまだ成長フェーズの会社だからこそ、面白い仕事ができますし、他ではできない経験値を積めることをアピールしたいです。どんどん拡大している会社ですので、若いうちから責任ある仕事に挑戦し、成長していけるでしょう。
外国人スタッフが多く活躍しているなど、グローバルな環境であることも大きな魅力です。仕事の場面だけでなく、例えばランチに行った際には各メンバーの食事や文化の話をするなど、日常会話をする機会も多くありますから、本人の意欲さえあれば英語のコミュニケーションスキルも伸ばしていける環境だと思います。
私は大学時代から人工衛星に関連した研究をしていましたが、Synspectiveではさまざまな職種の募集をしていますので、人工衛星に関わってこなかった方も活躍できるフィールドがあります。Synspectiveの事業内容や組織風土に少しでも興味を持っていただけたら、ぜひ応募を検討してほしいと考えています。
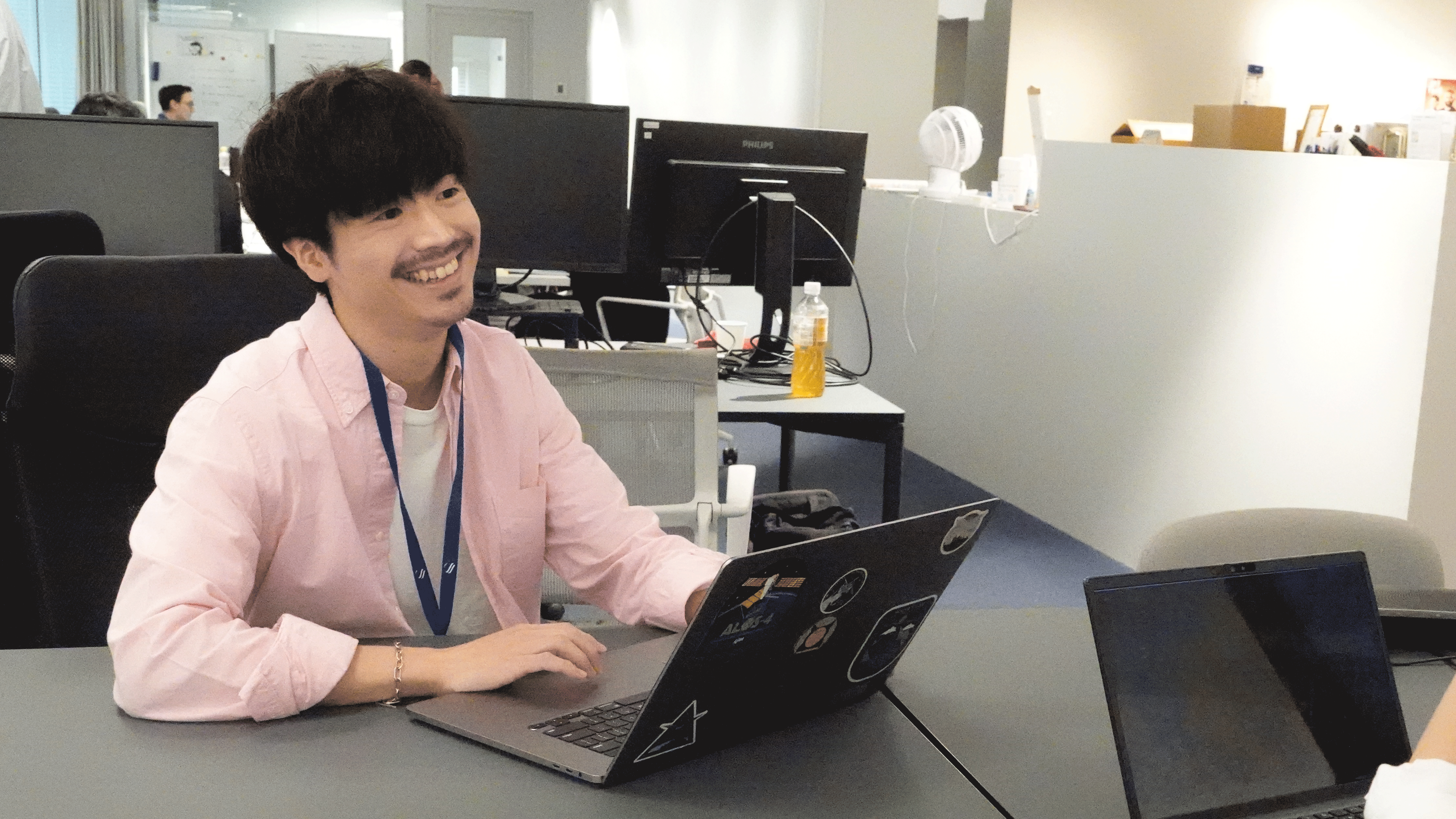
・年次に関係なく実力で評価。入社4年目からマネージャーを任せる「若手抜擢環境」
・宇宙技術で社会課題を解決。事業を通じて実感できる「社会貢献性」
・未経験領域への挑戦的なアサインで成長を促す「20代の活躍環境」