
東大院生に学ぶ「新しいアイディア」の生み出し方
はじめに
「現役東大大学院生による面白科学ブログ パルプンテ.com」を運営している、サイエンスパルプンテさんが、リアルイベントを開催するということで潜入してきました!
場所は、東大赤門の目の前にある学生無料のコミュニティー&イベントスペースPRECIOUS。

本編に入る前に、少し団体の紹介を。
SCIENCE PALPUNTEさんは、東大大学院生8名が所屬する団体。
生物から宇宙科学、地球科学、人工知能まで、専門が異なるメンバーが集まっており、 「科学を楽しむ」というモットーで、最先端の科学技術や学問を、専門ではない人にも分かりやすく発信されています。
※例えば、こんな興味深いエントリーも!
◎2017年のノーベル賞をもう予想!?「遺伝子を自在に編集できる」CRISPR-Cas9とは!?
◎東大生は、本当に「頭の出来」が違うのか?
今回は多分野交流学生セミナーと題し、通常内部で行っている研究発表会を一般公開するイベント。文系出身のshimaには、「最先端科学」ときくと非常にとっつきくいイメージですが……私の他にも文系の学科に所屬する学生参加者がちらほら。いざ突入です!
天文学では、系外惑星探査がアツイ

「今、天文学では系外惑星探査 がアツいんです…!!!」
そんなヨシキさんの一言から始まりました。
系外惑星探査といえば、昨年2月、NASAからの重大発表、で地球から約39光年離れた恒星「トラピスト1」のまわりに7つの地球型の惑星が見つかったことでも話題をさらいましたね。
系外惑星を発見するのに大きな役割を担っているのが、NASAが運用している宇宙望遠鏡ケプラー衛星。(宇宙望遠鏡=超望遠レンズが搭載されているのか、すごーい!と内心思っていましたが、ヨシキさんの解説によると全然違いました…汗)
ケプラー衛星とは、(超高性能の望遠レンズがついているのではなく)、明るさの測定や「星の固有振動を確認」することで、恒星の周りを惑星がどのように回っているのか?や、その恒星自体の内部構造などを解明出来るのだそう。
明るさの測定…?
固有振動を確認…??
内部構造を解明…???
ちょっと頭が混乱してきました…。ヨシキさんは、余裕の笑顔で続けます。
「簡単にいうと、Aという星の明るさを計測していたとしますよね。で、ある一定の間隔で減光しているということがわかったとします。そうすると、その星の前を、定期的になにかが横切っている…という仮説が立つじゃないですか」
な、なるほど…。
「そして、最近解明されたことなのですが、星って実はぶるぶる震えてるんですよね(=固有振動してるのです。)ケプラーでその振動を観測することによって、その星の大きさや、年齢や歴史などが見えてくるんです。これを星震学といいます。」
後から調べて見たところ、この星の振動、「星の音楽」とも言われているそうです。
確かに、楽器に置き換えて考えると、「小さい楽器であれば高い音が出て振動は細かい」、「大きな楽器であれば低い音がでて振動は幅広い」というのは理解ができますね。
「振動」から推測できる、その星の軌跡
KIC11145123…クレジットカードの番号ですか…??(心の声)
いえいえ、そうではありません。
KIC11145123はケプラー衛星によって発見されたA型星(=恒星のタイプの1つ)
「KIC11145123の振動を調べていくと、星の外側の方が、内部より早く回転している箇所があるのがわかったんです。例えば、フィギュアスケートのスピンを思い出してください。手を内側に入れるとスピンが早くなり、大きく広げるとスピンが遅くなりますよね。それと同じ原理で、星も本来は内側の方が早く回転しているはずなんですよ。だからこそ、このKIC11145123の現象はとてもめずらしいんです。」

「この現象から様々な仮説が立てられます。例えば、KIC11145123に、隕石が衝突した。その隕石が高速に回転をしており、その隕石がKIC11145123の内部に取り込まれある箇所のみが異常な回転をしているのではないか?とか。仮説はたくさんあります。振動を観測することで、その星の歴史が垣間みれますよね。」
「本日、色々なお話をしましたが、是非みなさんに知っていただきたいことは、『星震学』という学問があること。そしてそれを用いることによって、実際には触れられない遠くはなれた星の、在り方や取り巻く環境が推測できる、可能性があるということです。」
なるほど…ヨシキさんの「星の振動でおかれている環境が推測できる」という言葉が少しずつ分かってきました。
こうして、約30分程でヨシキさんの濃密なプレゼンが終了。
天文学に全く馴染みのないshimaでも、骨格が理解できる池上彰さんバリの解説。
飽きることなく引き込まれてしまいました。拍手。
「常識を交ぜる」ことで新しいアイディアが生む
終了後、改めて彼らに、このイベントを開いている主旨を聞くとこんな答えが返ってきました。
「最初は、研究発表の練習の場として立ち上がったんです。違う専門の学生が集まって、予備知識がない人に、どう自分の研究を伝えていけばわかりやすいんだろう…相互チェックの場ですね。実は、サッカー部の有志がただ集まってやってただけなんです(笑) ただ、ある時期から、面白科学ブログなので外部への配信も始めました。ある特定の分野の研究をずっとやっていると固定概念ができてきちゃうんですよね。だからこそアイディアが浮かばなくなることもあります。なので、多くの人に、自分たちの研究を発信することで、質問をもらい、逆に異なる分野の「常識」に触れる。そして、
客観的に自分の「常識」を見つめること、周囲の「常識」を交じらせることによって、新しいアイディアを生んでいきたい
と思っているんです」このお話を聞いて、広告・企画に携わる人のバイブルでもある「アイディアの作り方(ジェームス・W・ヤング著/1988年出版」の一説を思い出しました。
『アイデアとは既存の要素の新しい組み合わせ以外の何ものでもない。』
著書の中では「特殊資料」と呼ばれていますが、【自分が携わる分野で深いリサーチをすることに寄って得られた専門知識】と、「一般資料」と呼ばれている、【好奇心を持って収集した様々な分野の情報や、普段の生活の中でキャッチアップした情報】、これを組み合わせることがアイディアの第一段階だ、という内容を伝えた一説です。
彼らの、自分の「常識」と周囲の「常識」を掛け合わせるという発想は、最先端科学の研究という範囲にとどまらず、新しい事業を創出するとき、新しい企画を立てるとき、ビジネスシーンでも、自身の学生生活の中でも活かせる要素がたくさんありそうです。
最先端科学に触れられたのは勿論ですが、「新しいアイディアのつくり方」という点でもとても勉強になるイベント参加となりました。
以上、irootsライター shimaがお届けしました!
―取材協力―
◎サイエンスパルプンテの皆さんhttp://www.science-palpunte.sakura.ne.jp/
※ブログのエントリーも興味深いものばかりです。
◎PRECIOUS(東大前・本郷店)の皆さん
https://en-precious.jp/

学生のためのコミュニティ&イベントスペースです。
普段は、カフェスペースとしても活用でき、ワンドリンク無料、wifi・電源完備の集中できる環境でした(赤門のすぐ目の前で、とてもおしゃれな空間です)
第一線で活躍する社会人との交流も定期的に行われているそう。
外にも、慶應前、阪大前、神大前の4校にオープンしています。お近くにお立ち寄りの際は是非!
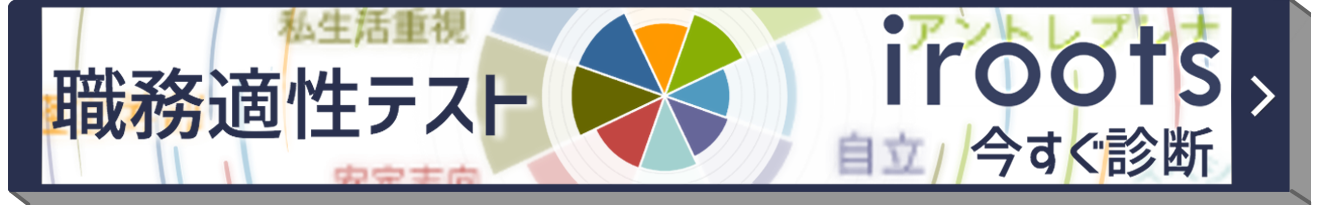
※本サイトに掲載している企業は、iroots利用企業とは一切関連がございませんのでご注意ください。また、掲載情報は、各企業のコーポレートサイト等広く一般的に周知がなされている事項に加え、就活生から得た情報を元に、当社学生ライターが中心に独自にコンテンツ化したものです。
内容については細心の注意を払っておりますが、ご利用に際しては、閲覧者各人の責任のもとにこれをご活用いただけますようお願い申し上げます。
内容については細心の注意を払っておりますが、ご利用に際しては、閲覧者各人の責任のもとにこれをご活用いただけますようお願い申し上げます。
© en Inc.|エン株式会社(旧:エン・ジャパン株式会社)











