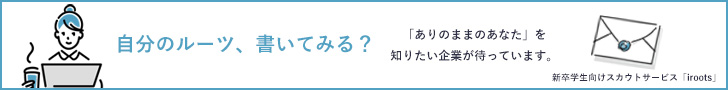この会社で、自分はどんな未来を描けるだろう?――。ファーストキャリアという重要な選択を前に、そんな期待を抱える就活生へ。「Vision Talks」は、企業の未来を創り、その舵を取るリーダーたちが自らの言葉で、会社の未来像、そしてこれから仲間になる若手への想いを語る企画です。今回は株式会社湖池屋の執行役員人事部長 岡野 栄次郎さんにお話を伺いました。>>irootsへのログインはこちら
Interviewee’s Profile
創業:1953年 従業員数:1,100名(2025年3月31日現在※連結)
日本産じゃがいも100%にこだわったポテトチップスをはじめ、数々のロングセラーブランドを持つ国内有数のスナック菓子メーカー。創業以来の日本の誇りを大切にしながら、スナックと食事の境界を狙う新市場創造や海外展開を加速。「未常識を形に」をスローガンに、食を通じた新たな価値創造に挑戦し続けている。
岡野 栄次郎/株式会社湖池屋 執行役員 人事部長
1992年に専門商社へ営業職として新卒入社。大手GMSの担当を経験し、1999年1月に株式会社湖池屋へ転職。転職後は北関東支店のセールスとしてキャリアが始まり、最年少(当時)でマネージャーのポジションとなる。2006年に最優秀社員賞を受賞。その後営業管理職としてCVS、GMS、DR、HCとあらゆる販売チャネルを担当しながらマネジメント業務を行う。2017年に営業本部営業戦略室長に就任し、営業全体の戦略立案を経験。2022年に現在のポストである人事部長となる。2025年執行役員就任。
- スナックの常識を超え、日本の誇りを世界へ。湖池屋が描く、食の未来と挑戦の現在地
- 「1年目から、即戦力」。老舗の常識を覆す、ベンチャーさながらの環境で“個の力”を磨く湖池屋流育成術
- 可能性を最大限に広げるために。多様な経験で「全社最適」を担う、次世代のジェネラリストへの期待
TOPICS
スナックの常識を超え、日本の誇りを世界へ。湖池屋が描く、食の未来と挑戦の現在地
Q1. 株式会社湖池屋が描く将来像やビジョンについて教えてください。
私たちのビジョンは、単にスナック菓子を作り続けることではありません。スナック菓子と食事、その境界線“業際(ぎょうさい)”を狙い、食の新たな可能性を切り拓いていくことです。
近年、若い方を中心に、食事を小分けにして摂る分食化が進んでいます。これは、従来の「1日3食」というスタイルに捉われず、食事そのものがより手軽で自由になっていることの表れです。私たちは、この変化の中に大きなチャンスがあると考えています。スナックという枠を超え、食事の領域へと事業を広げることで、人々のライフスタイルに寄り添う新しい価値を提供できるはずです。
そして、もう一つの大きな柱が海外事業の拡大です。海外売上を現在の2倍にしたいと考えています。国内市場が縮小傾向にあるから海外へ、という守りの発想だけではありません。私たちの海外展開は、もっと積極的な想いに貫かれています。
湖池屋は、創業から日本の誇りを大切にしてきました。例えば、ポテトチップスの原料には日本産じゃがいもを100%使用することを宣言し、地域の自治体と組んだ商品開発も積極的に行っています。私たちが目指すのは、この日本のものづくりへのこだわりと誇りを、世界中に知らしめていくこと。そのための、攻めの海外展開なのです。
Q2. そのビジョン実現に向けて、現在注力していることは何ですか?
壮大なビジョンも、日々の地道な挑戦なくしては実現できません。特に、食とスナックの業際を狙うという新市場の創造は、トライ&エラーの連続です。私たちの業界では「千三つ(せんみつ)」、つまり1000の新商品を発売しても、生き残るのは3つだけ、と言われるほど厳しい世界です。だからこそ、一つの失敗にめげることなく、そこから何を学び、次にどう活かすかをチームで、そして会社全体で考え抜く。その粘り強さが、未来のヒット商品を生み出すと信じています。
こうした変革をドライブさせるため、人材採用の考え方も進化しています。私たちが今、仲間として迎えたいのは、物事を一つの側面からだけでなく、多角的に捉えられる人。そして、失敗を恐れず、成功へ導くためのしなやかな強さ、いわゆるレジリエンスを持った方です。変化の激しい時代だからこそ、多様な視点が交わることで生まれる化学反応を、私たちは大切にしています。
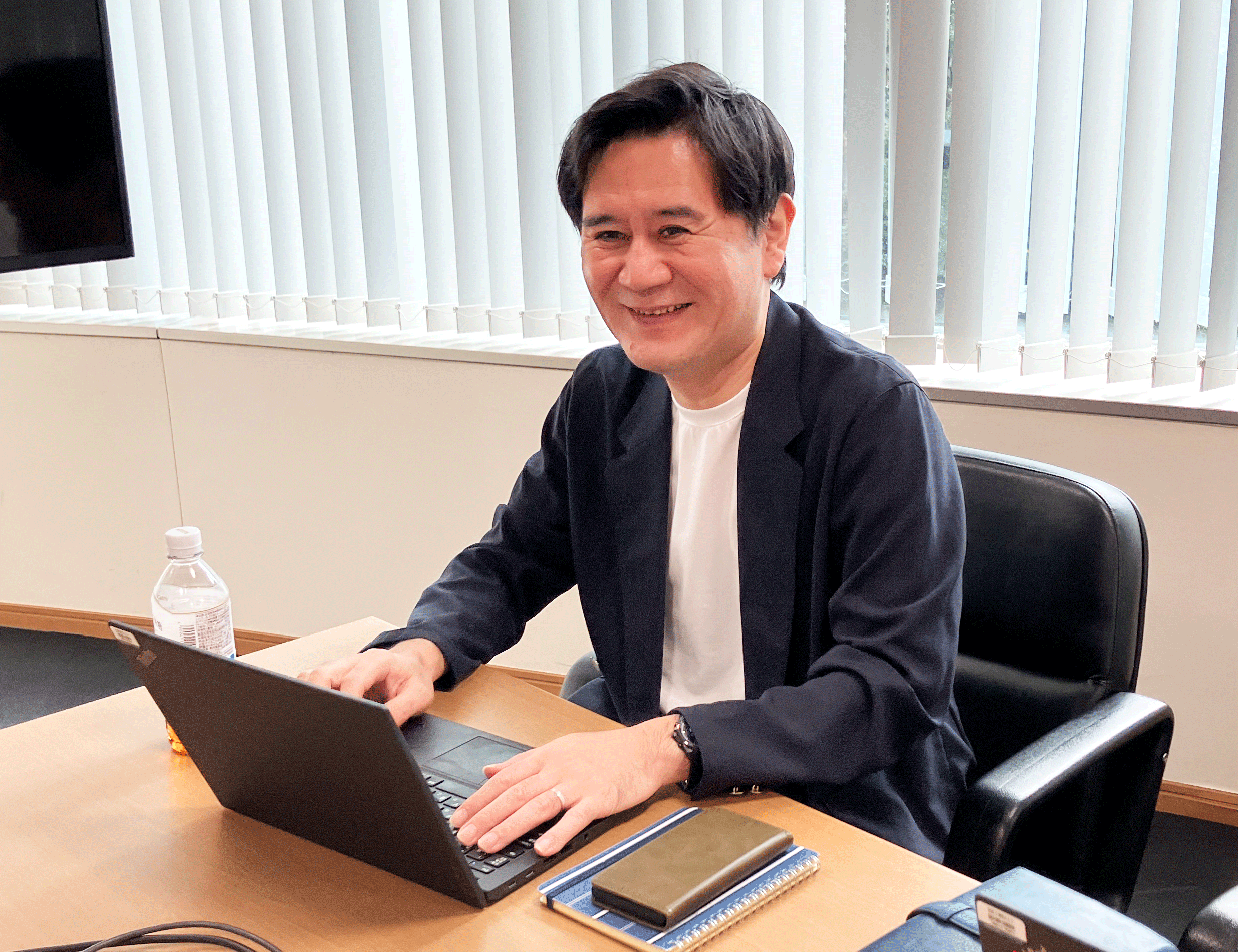
「1年目から、即戦力」。老舗の常識を覆す、ベンチャーさながらの環境で“個の力”を磨く湖池屋流育成術
Q3. 若手社員が成長するために、最も大切だとお考えのことは何ですか?
スキルや知識以前に、AIには代替できない人間的な能力を磨くことが、これからの時代を生き抜く上で何よりも大切だと考えています。
私たちの採用スローガンは「未常識を形に」です。世の中にまだ存在しないものを生み出すには、マニュアル通りの画一的な思考ではたどり着けません。自分らしく物事を捉え、自分の考えを深めていく。そのプロセスの中で、自分自身の内面をいかに成長させられるか。テクニカルなスキルは後からでも学べますが、この人間味あふれる探究心こそが、人を惹きつけ、誰も見たことのない価値を創造する源泉になると信じています。
Q4. 株式会社湖池屋には、どのような若手社員の成長環境がありますか?
湖池屋は創業70年を超える老舗ですが、若手の働き方は、ある意味で「ベンチャー企業」そのものです。私たちの育成方針を象徴するのは、1年目から即戦力として活躍してもらうという考え方です。
もちろん、入社後1ヶ月半は、社会人マナーやものづくりの基礎を学ぶ研修をしっかり行います。配属後は、OJTで実践的なスキルを学んだ後、すぐに責任ある仕事に挑戦してもらいます。なぜなら、「自分で体験してこそ得られる経験は何事にも代えがたい」と知っているからです。先輩の隣で長く見ているよりも、早くバッターボックスに立ち、成功も失敗も含めて自分自身の血肉にしてほしい。その方が、成長のスピードは圧倒的に速いのです。
10年で3部署を経験するというジョブローテーション制度も、若手の成長を後押しします。一つの領域に留まらず、多様な経験を積むことで、より広い視野と専門性を掛け合わせた「個の力」を磨くことができる。もちろん、挑戦には失敗がつきものですが、どの部署にも先輩や上司が必ずフォローしてくれる文化が根付いています。だからこそ、若手は安心して、思い切った挑戦ができるのです。
Q5. これまで若手社員に任せた仕事で、印象的なプロジェクトがあれば教えてください。
若手は皆、年次に関係なく会社の歴史を創るような仕事をしています。
また、人事部に配属された新入社員が、入社後すぐに次年度の新卒採用担当として、採用戦略の立案から実行までを担うこともあります。
年次を気にせず、誰もが会社の顔として最前線に立てる。それが湖池屋のリアルです。
可能性を最大限に広げるために。多様な経験で「全社最適」を担う、次世代のジェネラリストへの期待
Q6. 株式会社湖池屋を志望する若手社員に、どのようなことを期待していますか?
自分の好きなことだけでなく、興味のないことにもアンテナを張り、それを楽しむ工夫ができる人であってほしいと願っています。
仕事は、好きなことばかりではありません。むしろ、地道で大変なことの方が多いかもしれない。その7〜8割の大変な仕事を、いかに自分なりに面白くできるか。SNSで自分の興味がある情報だけが流れてくる時代だからこそ、あえて自分の知らない世界に足を踏み入れ、知見を広げる姿勢が、あなたの価値を大きく高めます。一見関係ないように思えた知識が、いつか自分の専門分野と結びつき、誰も思いつかなかったイノベーションを生む。私たちは、そんな化学反応が生まれる瞬間を何度も見てきました。だからこそ、学生の皆さんには自分の世界に閉じこもらず、あらゆる物事から学び、成長の糧にできる探究心を期待しています。
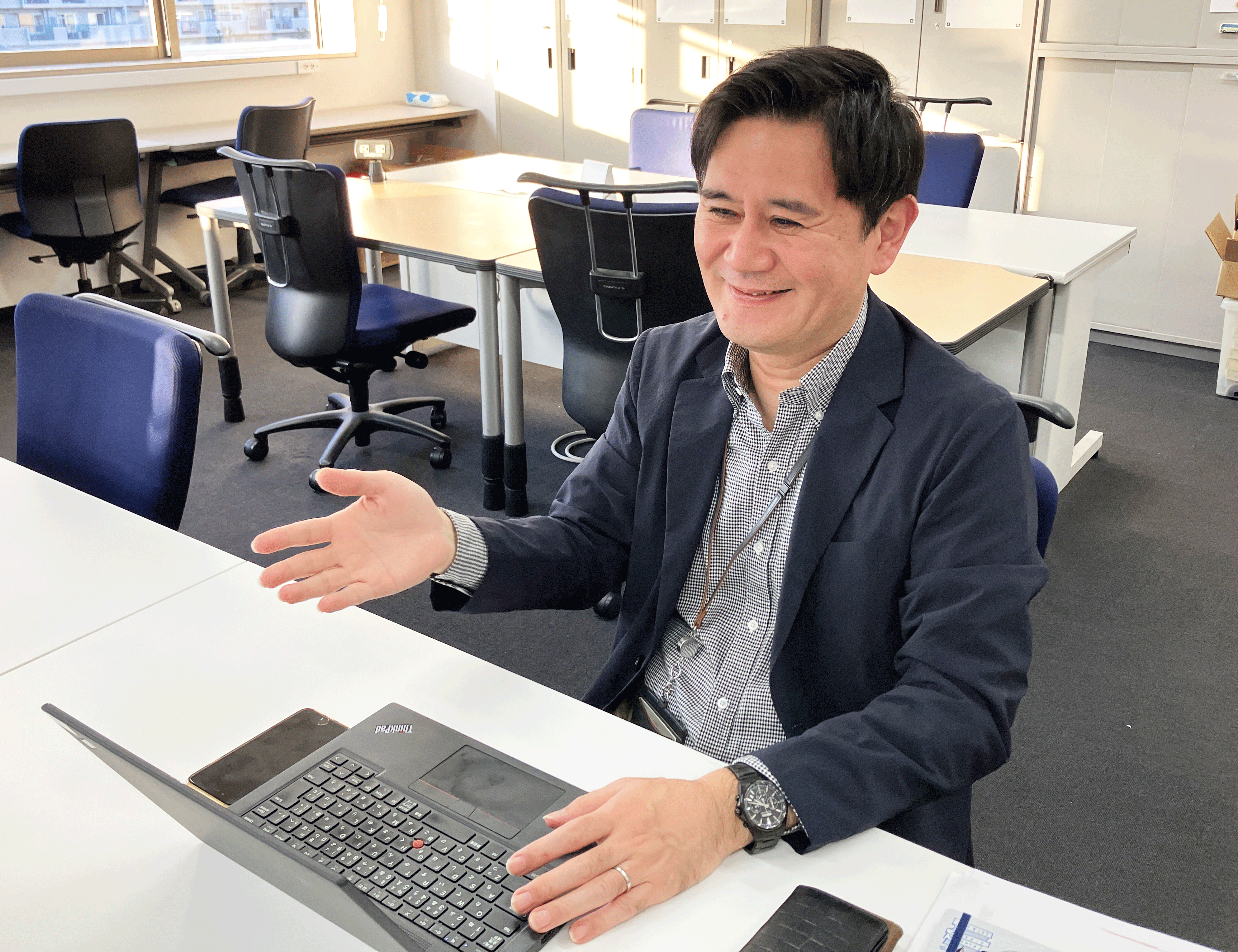
Q7. 最後に、就職活動に励む学生へメッセージ・エールをお願いします。
皆さんにお伝えしたいのは、「あなたの可能性は無限だ」ということです。その可能性を最大限に広げてほしいという想いから、私たちは職種を限定せずに多様な経験を積んでもらう「ジェネラリスト採用」という形を選んでいます。
学生時代に抱く職種のイメージと、実際の仕事には、往々にしてギャップがあります。若いうちから一つの職種に限定されることは、自らの可能性を狭めてしまうことにもなりかねません。私たちは、若いうちにこそ様々な経験を積み、自分の可能性を広げていってほしいのです。
湖池屋では、部門間の壁を取り払うため、毎週すべての部門長が集まり課題を議論する「変化対応会議」を行っています。製造部門の課題を、営業部門のアイデアで解決することもある。これは、各部門長が他部署の事情を理解し、「全社最適」の視点を持っているからこそできることです。私たちは、こうした多様な経験を積んだ人材こそが、会社の未来を担う力になると信じています。
ファーストキャリアは、あなたの人生を大きく左右します。だからこそ、今の気持ちだけで可能性を閉ざさないでほしい。湖池屋というフィールドで様々な経験を積み、未来の会社を担う、視野の広いリーダーへと成長していきませんか。皆さんの無限の可能性に出会えることを、心から楽しみにしています。