
ビジネスするなら知っておきたいフレームワーク10選(後編)
こんにちは。irootsインターンのKobaです。将棋の藤井4段はコンピューターと戦いまくったり、詰め将棋を解きまくったりして将棋の腕を鍛えたらしいですね。要するに将棋の「コツ」を学び、実践し続けたってことですね。この記事でもビジネスにおける「コツ」を、僕なりに楽しくまとめていきます。
ビジネスするなら知っておきたいフレームワーク集(前編)はこちらの記事へ
⑥PEST分析
PEST分析とは、マーケティングで有名なフィリップ・コトラー教授が編み出した手法で、事業を取り巻くマクロ環境を分析するフレームワークとなっています。マクロ環境はPolitical Factors(政治的要因)、Economic Factors(経済的要因)、Social Cultural Factors(社会的要因)、Technological Factors(技術的要因)の大きく4つに分類することができます。新規事業などを考える際、外部のマクロ環境を知ることは非常に大切になってきます。その時代、環境に適した事業を創造することが、事業成功における必須条件となっています。
例えばドローンがあります。ドローンは海外では日常でよく見かけますが、日本ではあまり見かけません。その理由として、航空法などの政府による規制(政治的要因)、もし被害を与えたとき、誰が責任をとるのかという集団責任追及の文化(社会的要因)、今の技術では、墜落などの被害を防ぐことはできない(技術的要因)などが挙げられます。よって現在の日本ではあまり流行しないということが判断できます。
⑦7S
7Sとはマッキンゼーが提唱した考えで、組織の整合をはかるためのチェックリストです。上段3つは「ハードのS」と呼ばれ、経営者の判断次第ですぐに変更することができます。一方、下段3つは「ソフトのS」と呼ばれ、変化するまでに時間がかかります。真ん中の「価値観」は上段と下段を繋ぐものとして特に重要とされています。これらの資産をしっかりと把握し、大切にしていくことで組織をより強固にすることができます。
例えばサッカーチームだと戦略(どういう形で攻撃するのか、守備するのか、フォーメーション)、組織(組織体制、育成方法)、システム(評価基準)は容易に変更することができます。一方、スタイル(チームの雰囲気)、組織としての能力(現在何位にいる力があるのか)、人材(選手)は容易に変えることができません。チームとしての価値観を監督と選手で一体となって共有することが大切となってきます。
⑧AIDMA、AISAS
AIDMAとは、Attention(認知、注目),Interest(興味、関心),Desire(欲求),Memory(記憶),Action(購買)の頭文字で消費者の購買プロセスを示しています。消費者がその商品や広告などを見て関心を持ち、「ほしい」という欲求が芽生え、脳に記憶され、購入に至るといった流れです。
近年では、SNSの台頭により「AISAS」というプロセスが注目されるようになりました。AISASでは、Attention(認知、注目),Interest(興味、関心)までは同じですが、その後Search(検索),Action(購買),Share(共有)となります。
例えば、Macbookを購入するとします。CMを見て新型が出たことを知り(認知)、買いたいと思い(関心)、どの型が自分に合うのかや、Windowsとの違いなどを調べます(検索)。そこで出てきたものを他のものと比較検討し購買します(購買)。そして「このパソコンよかった」と、友達に直接口頭で伝えたりSNSで拡散したりします(共有)。
⑨イノベーター理論、キャズム理論
出典: 【キャズム理論】マーケティングの深い溝を乗り越えるためには?
イノベーター理論とは、消費者はイノベーター、アーリーアダプター、アーリーマジョリティ、レイトマジョリティ、ラガードの大きく5つのグループに分類できるという理論です。アーリーアダプターまでが全体の消費者の16%とされていて、アーリーアダプターに商品が浸透すると、その後多くの消費者に受け入れられるだろうとされています。
しかし、キャズム理論ではアーリーアダプターとアーリーマジョリティの間に大きな溝があるとし、それぞれ購買する理由に差があるという理論です。アーリーアダプターまでの消費者は、商品の「新規性」や他者が持っていないものを手に入れたという「特別感」に魅力を感じて商品を購入します。一方、アーリーアダプター以降の消費者は他の人が使っているため安心して使えるという「安心感」があるため商品を購入します。
つまり、アーリーアダプターとアーリーマジョリティでは求めるものが違っているので、キャズムを超えて多くの人に使われるようにするためには、段階に応じて、マーケティングのアプローチを変えていくことが必要だということです。
例として、スマートフォンの登場が挙げられます。2000年代後半に発売した当初、多くのイノベーターの人やアーリーアダプターの人が家電量販店の前に並んで購入しました。しかし、一時の流行だけで全員に普及しないだろうというのが大半の人の考えでした。ところが、CMの登場やLINEなどのメッセージアプリの登場によりスマートフォンが非常に便利なものでみんな買っていることがわかると、キャズムを超えてアーリーマジョリティの人やレイトマジョリティーの人々も購入するようになりました。
⑩マズローの欲求階層説
最後に、マズローの欲求階層説を紹介します。人間の欲求は5段階に分かれていて、低次の欲求が満たされると高次の欲求を求めるようになるというものです。
生理的欲求では人間の活動を行っていくためには栄養を摂取したり睡眠を行わなければならないため「食べたい、眠りたい」などの本能的な欲求が発生します。
その次の安全欲求では、自分の身に危険がある状態だと自分の身を守ることを本能的に優先するため、「安心して暮らしたい」「セキュリティがしっかりしている家に住みたい」などといった欲求が発生します。
とりあえず自分が生きていくことができるということがわかってくると、今度は「誰かと一緒に居たい」「何かしらのコミュニティに入りたい」という社会的欲求が発生します。
社会的欲求が満たされると、次はその組織から認められたい尊厳欲求が発生します。尊厳欲求は「ありがとう」や「○○がいたから助かった」など、他者に自分の存在を認めてもらうことによって満たすことができます。
最後に、自己実現の欲求が発生します。自己実現の欲求では「他者に影響を及ぼしたい」「自分の力を社会に役立てたい」など求めるようになります。
例えば、途上国では生理的欲求や安全欲求を持つ人々が多く、「なんとしてでも安全に生きたい」という考えを持っている人が多いです。その結果、他人の財産を奪ったりするなど治安が悪く、犯罪が多くなっています。また、仕事を選ぶ基準として給与を挙げる人々が多いです。それは自分や家族が安全に暮らすためにまず必要なのは給与であるといった発想からでしょう。一方、先進国では「社会貢献をしたい」「人の役に立つ仕事がしたい」など、給与とは違った理由で仕事を選ぶ人も増えてきました。先進国では生理的欲求や安全欲求が基本的に満たされているため、より高度な次元の欲求が発生し、その結果尊厳欲求や自己実現欲求で仕事を選ぶ人が増えてくるようになったのでしょう。
僕自身も、今まで育ててもらった社会に対し貢献したいという思いがありますが、そのためには最低限の生活が必要であると考えています。仕事を通じて社会に対し貢献し続け、その対価として収入をもらいながら生活していきたいです。
ビジネスするなら知っておきたいフレームワーク集(前編)はこちらへ
―この記事を書いた人―
小林 良輔iroots インターン
早稲田大学商学部在学中。日系企業・タイ企業のビジネスマッチングサイト、子育てメディアのインターンを経てiroots編集部へ。irootsでは主に企画、マーケティング、記事作成を担当。趣味は散歩。
関連記事もチェックしてみよう
> これだけは押さえておきたい最低限の知識(インターネット業界編)
>これだけは押さえておきたい最低限の知識(人材業界編)
>これだけは押さえておきたい最低限の知識(広告業界編)
★各種コラム
>人材業界18年。就活を見てて分かったこと
>未来志向な夢との付き合い方:金谷武明
>若手ベンチャーキャピタリスト人生を語る
>未来を創る源泉は、過去の経験に眠っている
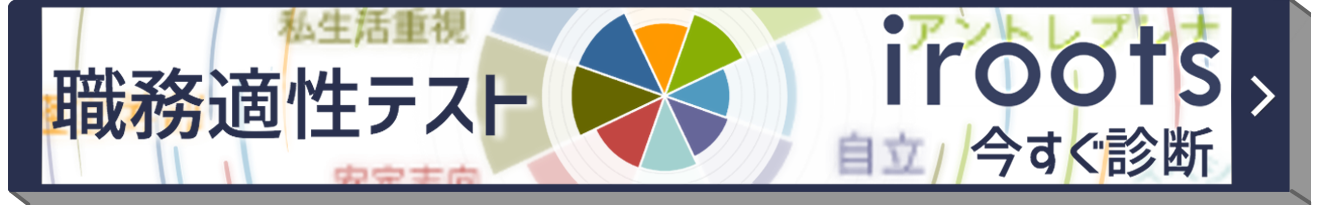
※本サイトに掲載している企業は、iroots利用企業とは一切関連がございませんのでご注意ください。また、掲載情報は、各企業のコーポレートサイト等広く一般的に周知がなされている事項に加え、就活生から得た情報を元に、当社学生ライターが中心に独自にコンテンツ化したものです。
内容については細心の注意を払っておりますが、ご利用に際しては、閲覧者各人の責任のもとにこれをご活用いただけますようお願い申し上げます。
内容については細心の注意を払っておりますが、ご利用に際しては、閲覧者各人の責任のもとにこれをご活用いただけますようお願い申し上げます。
Copyright © 2025 en-japan inc. All Rights Reserved.
















