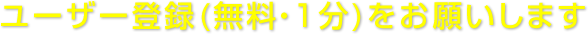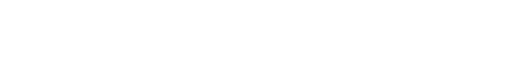インフラ業界の「これだけは押さえておくべき」最低限の知識│就活研究記事
公共性が高く、安定した市場を持つインフラ業界は就活生の間でも人気の高い業界の1つです。近年は少子化による国内市場の縮小が懸念され、新たな市場を求めて海外進出を積極的に進めている企業もあり、ダイナミックなビジネスフィールドが期待される業界でもあります。
今回は、そんなインフラ業界に興味を持つ就活生の皆さんに、インフラ業界の歴史から、業界概要、市場規模、最近の動向のほか、気になる年収やインフラ業界に向く人物像などを紹介します。
日本におけるエネルギー産業の歴史
日本でガス・電気の事業が始まったのは明治初期。石炭・石油が本格的な産業となったのも同時代に入ってからです。明治維新によって西欧の先進技術が導入され、日本の近代エネルギー産業は、まさに文明開化と共に産声を上げました。
大正時代に入ると、近代産業の発展にともない、交通網をはじめ、ガス、電気、水道などのインフラ整備も本格化しました。明治時代のエネルギー産業の黎明期から、大正時代を経て、エネルギー産業の近代化は昭和時代に完成します。
1950年代~1960年代は、エネルギーの主役が石炭から石油に交代した「エネルギー革命」の時代。マイカー時代の到来に加え、重化学工業の発展が大きく関係しています。
1966年日本原子力発電株式会社が、日本初の商業用原子炉「東海発電所」を建設し、営業運転を開始。ここから日本の原子力発電が広まっていきました。
高度経済成長を遂げ、経済大国となった日本をおそったのが2度にわたるオイルショック。1970~1980年代は、このオイルショックを機に、石油に依存したエネルギー体制からの脱却が図られます。
1980年代後半から1990年代にかけては、地球温暖化問題がエネルギー政策に大きな影響を与えはじめ、新エネルギーが台頭。また「電力・ガス改革」の動きが活発化しました。
2011年東京電力・福島第一原子力発電所の事故をきっかけに、日本はエネルギー政策をゼロベースで見直す必要に迫られました。同震災以降は原子力発電所が停止したため、原子力をカバーする形で火力発電所の稼働率が上昇。
また、新エネルギーとして期待される水素については、2009年、世界にさきがけて「家庭用燃料電池(エネファーム)」が市場に投入されています。
エネルギー産業には最終ゴールがありません。常に時代の要請に応え、その時点でベストといえる形を模索していくこと、そして、より安全で地球環境にもやさしいエネルギーが安定して供給されることが求められます。
社会基盤となる施設や仕組みを提供するインフラ業界
電気、ガス、水道、エネルギー、鉄道、航空など、社会の基盤となる施設や仕組みを提供する、インフラ産業。同産業に関わりのある、各業界の概要と主な企業を紹介します。
電気を供給・発電する電気事業を主要な収益源としているのが電力事業者です。2016年4月1日電力の小売り全面自由化以降は、旧一般電気事業者という呼称で表現されています。
主な電気事業者: 東京電力、 関西電力、 中部電力、 東北電力、 九州電力、 四国電力、 中国電力、 北海道電力、 北陸電力、 沖縄電力
ガス供給事業を営むガス事業会社。2017年4月1日ガス事業法の改正以前は一般ガス事業者と呼ばれていましたが、現在は「ガス小売事業者」であり、かつ「一般ガス導管事業者」でも「ガス製造事業者」でもあります。
主なガス事業者: 東京ガス、 大阪ガス、 東邦ガス、 西部ガス、 静岡ガス
水道で飲用に適する水を供給する事業のうち、給水人口が100人を超えるものを水道事業と呼びます。ほぼすべてが地方公営企業で行われています。
主な水道事業者:東京都水道局、横浜市水道局、名古屋市上下水道局、大阪市水道局、札幌市水道局、福岡市水道局など
石油の精製・元売りといった下流事業はもちろん、探鉱・開発・生産という上流事業も手がけるようになってきた有力会社としては以下のグループが挙げられます。
主な石油会社: JXTGホールディングス、 出光興産、 コスモエネルギーホールディングスなど
人・モノの移動手段として鉄道を運行している鉄道会社。それらの多くは鉄道事業のほかにも、駅開発を軸に不動産や小売業、ホテル、レジャー施設など、異業種の事業を運営するケースが多くなっています。
主な鉄道会社: JR東日本、 JR東海、 JR西日本、 近鉄グループホールディングス、 東京急行電鉄、 阪急阪神ホールディングス、名古屋鉄道、東武鉄道、 西武ホールディングス、 小田急電鉄など
航空会社は、大規模航空事業者と格安航空会社に大別できるほか、人を輸送する旅客分野とモノを輸送する貨物分野という2つの事業にも分けることができます。近年、インバウンド需要に恵まれ旅客は堅調に推移。一方、貨物も、国際貨物は増加傾向にあり好調です。
主な航空会社: ANAホールディングス、 日本航空、AIRDO、ソラシドエア、スターフライヤー、JAL CARGO、日本貨物航空など
政府主導の大改革。電力・ガスの自由化とは?
今まで電気といえば、東京電力や関西電力など、各地域の電力会社だけが販売しており、消費者は「どの会社から電気を買うか」という選択肢はありませんでした。
しかし、2016年4月1日電気小売業への参入が全面自由化されたため、消費者は電力会社や料金メニューを自由に選択できるようになりました。様々な事業者が電気小売市場に参入することで競争が活性化し、多彩な料金・サービスの登場が期待されています。
さらに、2017年4月1日都市ガスの小売全面自由化もスタート。電気と同様に、新規参入を通じた競争の促進が期待されるとともに、すべての消費者がガス会社や料金メニューを選択できるようになりました。
総合マーケティングビジネスの富士経済が行った調査の結果によると、2016年度以降、消費者による新電力への切り替えや販売電力量の増加が継続しているといいます。
しかし、家庭用を中心とした低圧では、大手都市ガス会社や通信会社が市場をけん引している一方で、高圧以上では旧一般電気事業者の価格に対抗できる新電力は少ない状況となっています。
また、国内の電力販売量全体は横ばいから微減で推移しており、2025年度の新電力シェア率は30%を超えるとみられています。
国内事情とは逆行!世界で増加し続ける電気・ガス需要
日本国内では、少子高齢化による人口減少などにより、電力・ガス産業を取り巻く経営環境は厳しさを増しています。前述したように、電力市場は2016年4月に、ガス市場は2017年4月に小売が全面的に自由化。これにより、事業者間の競争や新規事業者の参入がますます盛んになり、世界で競争できる日本のエネルギー企業の活躍も期待されています。
世界に目を移してみると、電力・ガスの需要は増加傾向にあります。なかでもアジア諸国では、天然ガスの需要などが大きく伸びており、今後も需要の拡大が続く見込みです。
■世界における電力・ガスの需要
出典: 電力・ガス産業の大きな成長ポテンシャル~グローバル化|電力・ガス|スペシャルコンテンツ|資源エネルギー庁
日本の電力・ガス産業の成長には海外展開や新たな市場獲得が欠かせませんが、産業競争力の強化にとどまらず、国内のエネルギー供給や調達力の向上を通じた多様なエネルギー源の確保にも役立つものです。
さらには、日本の電力・ガス分野における技術が他国、とりわけ途上国の経済開発や温室効果ガス削減に貢献できるという点でも、大きな意義があると言えるでしょう。
IoTやAIを活用した、新たなモビリティサービスへの取り組み
出典: 日本初 大型バスによる営業運行での自動運転実証実験を実施!~I▫TOP横浜「路線バス自動運転プロジェクト」始動~|横浜市のプレスリリース
都市における道路混雑やドライバー不足、地方では高齢化にともなう地域交通サービスの縮小などへの対策として、政府が中心となり、自動運転車による公道での実証実験が推進されています。
また、各交通事業者も、MaaS (モビリティ・アズ・ア・サービス) 、バス・タクシー運行時におけるAI(人工知能)や自動運転技術の活用など、新たなモビリティサービスの取り組みを開始。
例えば、横浜市と相鉄バス、群馬大学は「路線バス自動運転プロジェクト」を立ち上げ、本プロジェクトの一環として、日本初の大型路線バスを使用した自動運転の実証実験を行いました。
自動運転バスによる地域交通課題の解決を目指すだけでなく、公共交通分野での新たな事業展開の可能性を広げるとともに、都市のあり方にも多大なインパクトをもたらす可能性があると期待されています。
インフラ業界の仕事。向いているのはこんな人
インフラ産業には、電気、ガス、水道、エネルギー、鉄道、航空など、様々な業界があります。今回はその中でも、大手ガス会社の仕事内容や、その業界に向いている人物像を紹介します。
ガス会社が行う「ガス事業」では、「海外」や「原料調達」「電力事業計画・エンジニアリング」「生産技術」「パイプライン技術」など、幅広い業務が生じます。ここでは、営業や海外事業に関する仕事内容を紹介します。
営業職には「家庭用」「業務・産業用」と2種類の分野があります。家庭用の営業職は、暮らしの快適性を向上させるエネファーム機器などをマンションディベロッパーやハウスメーカーに提案します。
一方、業務・産業用の営業職は、CO2の排出量を減らしたい、エネルギーコストを減らしたいなどと考える、学校・病院・官公庁・工場などへの営業に携わります。
また、海外事業には、「上流事業」と「中下流事業」があります。上流事業では、エネルギー安定供給のため、オーストラリアや北米においてガス田開発に投資・参入し、プロジェクトの進捗管理を行います。
中下流事業では、自社が持つ都市ガス・電力事業の運営・技術ノウハウを活用し、各国においてLNG基地の建設やパイプライン敷設、発電事業といったインフラ整備に参入。収益源だけでなく、インフラ整備による社会貢献も目指します。
ある大手ガス会社が求める人物像として、「公益的使命や社会的責任を果たす事ができる人」「グループ企業や協力企業などパートナーとの協働ができる人」を挙げています。このような志向を持って仕事に取り組んでいきたい人に向いている業界です。
インフラ業界の年収ランキング。トップはENEOSグローブ
続いて、インフラ業界で働くうえで気になる平均年収について、東洋経済オンラインの「総合職の平均年収が高い会社ランキング300」を参考に以下のランキングにまとめました。インフラ業界(電力・ガス、海運・空運、鉄道)の企業を選出したところ、8社が挙げられています。
■インフラ業界平均年収トップ8企業
出典: 「総合職の平均年収が高い会社」ランキング300 | 就職四季報プラスワン | 東洋経済オンライン | 経済ニュースの新基準
インフラ業界の平均年収は高水準と言えるでしょう。トップは唯一の1,000万越えであるENEOSグローブ。液化石油ガスの輸入・販売を行っています。三井丸紅液化ガスと、JX日鉱日石エネルギーのLPガス事業を統合したJXTGグループの会社です。
わずかの差で第2位となったのが、エネルギー会社の1つであるアストモスエネルギー。出光興産グループと三菱商事グループの液化石油ガス部門が統合して発足したLPガス商社です。
また、3位以下は海運業界の企業が占めており、好不況の波が比較的大きいという側面もあるものの、高水準の年収が見込めそうです。
エネルギーに関するインフラ業界の関連用語
電力自由化などを背景に、エネルギービジネスに関する変革期にある日本。大規模かつ集中型の火力発電や水力発電など、需要に合わせて供給を行うシステムが使用されてきましたが、時代が進み、IoT(モノがインターネットに接続され、相互に制御する仕組み)を活用した仮想的な発電所の構想が立ち上がりました。
その中の一つに「ERAB」という電力エネルギーに関する新しい取り組みがあります。関連する用語をみていきましょう。
■ERAB
「エネルギー・リソース・アグリゲーション・ビジネス」の英頭文字の略。IoTを用い、需要家が保有する分散エネルギー機器と電力の消費量をエネルギー・リソース(蓄電池・太陽光・ディマンドリスポンスなど)として束ねることで、1つの発電所のように機能できるようにするビジネス。
■DR
「ディマンド・レスポンス」の英頭文字の略。需要家側の余剰エネルギーを制御することで、電力需要パターンを変化させること。DRは需要制御のパターンによって、「下げDR(需要を抑制)」と「上げDR(需要を創出)」の2つに区分されます。
例えば、下げDRなら、電気のピーク需要時に需要機器の出力を落として需要を減らします。上げDRなら再生可能エネルギーなどの余剰エネルギーを需要機器の稼働によって消費したり、蓄電池に充電したりします。
■
ネガワット取引
また、需要制御には、電気料金設定によって需要を制御する「電力料金型」と、需要家が業者と契約し、業者の要請に応じて需要の抑制をする「インセンティブ型」があります。特にインセンティブ型の下げDRのことを「ネガワット取引」と呼んでいます。
■アグリゲーター
需要家の電力需要を束ねて効果的にエネルギーマネジメントサービスを提供する、地方公共団体や非営利団体等を指します。
自ら電力の集中管理システムを設置し、エネルギー管理支援サービス・電力売買・送電サービスなどのサービス仲介を行っています。
フィンテックから転身した電力小売ベンチャー企業。目指すビジネスモデルとは?
出典: あしたでんき(TRENDE)
電力販売から家庭向け太陽光発電設備・蓄電池導入、それらが発電・蓄電した電力を他の家庭等と直接売買できるモデル(P2P電力取引)の構築などを行う電力小売りベンチャー、TRENDE(トレンディ)。
東京電力ホールディングスが出資し、2人の起業家によって設立されました。そんな同社が注力するのは主力の電力小売り事業よりも、電力のP2P取引プラットフォームの構築と、それを活用した再生可能エネルギーの普及です。
さらに、現在の「電気を売る」というビジネスは、ゆくゆく、電力の提供を通して得られるデータを収集・分析・加工することで、新たなビジネスを作っていくモデルに切り替わるとのこと。TRENDEは、今後、データビジネスが収益の中心になっていくようです。
東京電力ホールディングスとは一線を画するユニークな企業の代表を務めるのは、金融業界出身の妹尾氏とチャー氏。両者がフィンテック(金融と技術を組み合わせた造語)でつちかった革新的なサービスが、エネルギー業界にも影響を与えそうですね。TRENDEの動向に期待が高まります。
インフラ業界に興味があるなら必ずおさえておきたいインターン情報
最後に、東京電力ホールディングス、東京ガス、JR東日本、JXTGエ�
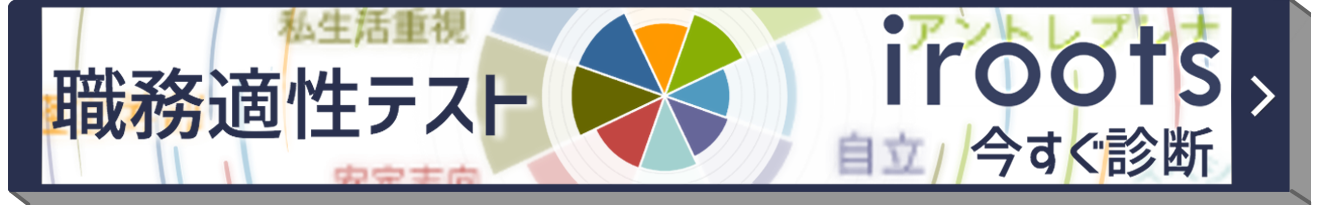
電力の小売全面自由化って何?|電力小売全面自由化|資源エネルギー庁
ガスの小売全面自由化とは|ガス小売全面自由化|資源エネルギー庁
富士経済、電力・ガス自由化市場調査結果を発表:日本経済新聞
自動運転バス
職種と業務領域 | 職種・仕事について | 東京ガス新卒採用サイト
ERABとは | ネガワット取引もそのひとつ:電力事業者向け顧客料金計算システム Enability - エネルギーソリューション【日本ユニシス】
「電力会社の競合はAmazonやAppleになる」、異色の東電ベンチャーが描く電力ビジネスの未来 (1/3) - スマートジャパン
東京電力ホールディングス 2019インターンシップ マイページ
東京ガス : 採用情報 / 3DAYS INTERNSHIP 2019 東京ガス、ミライキカク
インターンシップ:JR東日本
JXTGエネルギー事務系インターンシップ
インターンシップ|ANA 採用情報
ANAホールディングスのインターン体験記一覧 - みん就(みんなの就職活動日記)
内容については細心の注意を払っておりますが、ご利用に際しては、閲覧者各人の責任のもとにこれをご活用いただけますようお願い申し上げます。
© en Inc.|エン株式会社(旧:エン・ジャパン株式会社)


サービス・インフラ
人気記事


メーカー
人気記事


ソフトウェア・情報処理
人気記事


サービス・インフラ
人気記事

{{article.title_chip}}
人気記事
NEW


メーカー
人気記事


メーカー
人気記事


サービス・インフラ
人気記事


サービス・インフラ
人気記事

{{article.title_chip}}
人気記事
NEW